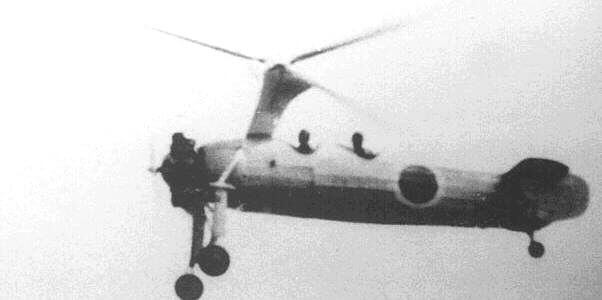| カ号観測機一型 |
| 全 長 | 6.95m |
| 全 幅 | 10.60m(ローター含む) |
| 全 高 | 3.10m |
| 主翼面積 | |
| 自 重 | 750kg |
| 航続距離 | 360km |
| 発動機 馬力 | 「アルグスAc10C」空冷倒立V型8気筒(神戸製鋼) 240馬力×2 |
| 最大速度 | 165km/h |
| 武 装 | 60kg爆雷1発 |
| 連 コードネーム | |
| 製 造 | 萱場製作所・神戸製鋼所 |
| 設計者 |
ヘリコプター?違います 構造が全く異なるオートジャイロとは
【カ号観測機】を語る上では100%付きまとう問題があります。
当然、【カ号観測機】が分類されているオートジャイロという機体そのものです。
今では少なくとも社会という大きな組織内で見ることはほとんどなくなり、個人が所有しているケースが大半です。
シンプルなデザインから、かなりスタイリッシュなものまで種類も豊富で、もちろん自家用飛行機よりも劇的に安いですから、空中散歩などに向いている回転翼機です。
この回転翼機にはもちろんヘリコプターも含まれますが、ヘリコプターとオートジャイロの共通点は、まさにこの回転翼機であるという点だけです。
他の一切が異なります。
まず、オートジャイロには機体の上にどでかいプロペラがありますが、それとは別に飛行機と同じく前方にもプロペラがあります(現代のオートジャイロは後ろにプロペラがあるタイプも存在します)。
ヘリコプターには通常機体の上のプロペラしかありませんが、ではオートジャイロの前方についているプロペラは何のためにあるのでしょうか。
当たり前ですが、このプロペラは、他の飛行機と同様に飛ぶためにあります。
じゃあ上のプロペラは何でしょうか?
ここがヘリコプターと決定的に違うところです。
ヘリコプターは機体上のプロペラを回して無滑走で浮上、飛行しますが、オートジャイロの機体上のプロペラは動力で動くわけではありません。
言ってしまえば、取り付けてあるだけです。
しかしこの大きさがあれば、ちゃんと離陸することができるのです。
通常、前方のプロペラを回すと当然ですが空気が前方から後方へ勢い良く送り込まれ、飛行機は速度を出して離陸へと向かって滑走を始めます。
その時の空気はどこに向かっているかというと、そのまま真後ろに向かうのではなく上へと送り出されています。
揚力装置という言葉がよく出てきますが、これはこのプロペラの回転によって発生した上昇気流を効率よく受け止めて機体の上昇を補助する装置です。
おわかりでしょうか。
この時下から受けた上昇気流を受けたプロペラがどんどん回転し、一気に機体を上に持ち上げるのです。
つまり、この大きなプロペラは大きな揚力装置とも言えるのです。
この2つのプロペラを使うことで、ヘリコプターのように全くの無滑走で浮上することはできませんが、非常に短距離で離陸することができるのがオートジャイロの最大の魅力でした。
実はヘリコプターのように機体の上部のプロペラだけで飛行する機体のほうが研究の歴史は圧倒的に古く、オートジャイロはその回転翼機という大きな研究の中で生まれた産物です。
明治44年/1911年にオーストリア人のルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが研究し、大正12年にスペイン人のフアン・デ・ラ・シエルバが初飛行に成功しました。
この頃のヘリコプターには、設計上の問題はクリアできても構造に適したエンジンが存在しないという問題があり、レシプロエンジンではついに満足のいく性能を発揮することができませんでした。
戦後に軽量で大出力を発揮できるガスタービンエンジン(ジェットエンジンの一種)が開発されてから、ヘリコプターの研究は急速に進みます。
ヘリコプターがなかなか実用化されない中、ヘリコプターに近い運用ができるオートジャイロは軍用化を検討する国も多く、イギリス、アメリカ、スペイン、イタリア、そして我が日本で陸海軍が研究を進めていました。
陸軍にとっては当然どこでも使える短距離離発着は魅力的ですし、海軍にとっても艦上の狭い甲板からも発艦できるのであれば多くの艦艇に搭載することができます。
速度は出ませんが、例えば日本の【カ号観測機】のように、観測用としては低速でホバリングに近い飛行ができて、安定性能が高く、着艦にも距離をほとんど必要としないオートジャイロは、地味ながらも興味をそそる存在であることは間違いありませんでした。
陸上部隊の砲撃観測のはずが、舞台は海上、そして終戦へ
日本の【カ号観測機】へと話を進めましょう。
観測機という名の通り、【カ号観測機】は砲兵部隊の着弾観測のための機体として研究されることになりました。
【カ号観測機】には、実は陸軍航空本部ではなく技術本部が開発の主体となっていて、陸軍機につきものの「キ」番号が振られていません。
この他にも【テ号観測機】という観測機が研究されましたが(オートジャイロではありません)、これらも陸軍技術本部が担当した機体です。
ですが陸軍にオートジャイロがやってきたきっかけは、昭和8年/1933年に陸軍航空本部がアメリカから【ケレット K-3】というオートジャイロを2機購入したからです。
ちなみにその前年にはイギリスの【シェルヴァ C.19】という機体を海軍と朝日新聞社が1機ずつ購入しています。
ところが陸軍も海軍もこの機体を壊してしまい、さらに陸軍は昭和14年/1939年にもう一度アメリカから【ケレット KD-1A】を購入しますが、これも翌年に壊してしまいます。
朝日新聞社が購入した機体も突風に煽られて大破(のち復旧)しており、飛行条件も含めて扱いが大変難しい機体だったのでしょう。
ともあれ、陸軍のオートジャイロはこれで3機全部が壊れてしまいました。
陸軍はこの壊れた機体の扱いに悩んでいましたが、これに目を付けたのが航空本部ではなく技術本部でした。
すでに気球観測は航空機の開発によって廃れつつあり、これに代わる観測の役割をこのオートジャイロなら果たすことができると考えたのです。
まず、離発着距離が非常に短くてすみますから歩兵・砲兵部隊に随伴ができる。
【カ号観測機】の離陸距離は、向かい風があればなんと10m以下だったそうです。
続いて上空でほぼ静止状態での飛行が可能、さらにはそのまま旋回もできる。
とても戦闘には使えませんが、気球のように定点観測ができ、支援機としては理想的な性能を持っているのがオートジャイロでした。
技術本部は早速航空本部から【KD-1A】を入手し、これを萱場製作所(現KYB)へ持ち込んで修理を依頼します。
創業者の萱場資郎はちょうど近い将来誕生するであろうジェット機に関心を寄せており、この無尾翼の【KD-1A】の修復はあとできっと無尾翼ジェット機の研究に役に立つと考えて快諾しました。
まずは【KD-1A】を見事修復し、そして同時に製作も進めていた試作機とともに昭和16年/1941年5月にテスト飛行を行いました。
結果は良好だったため、間を置かずに技術本部はこれをベースとして、国産オートジャイロの製作を萱場製作所と神戸製鋼所に指示します。
胴体部分は萱場製作所が、エンジンやプロペラ、ローター部分などは神戸製鋼所が受け持ちました。
構造は至ってシンプルで、基本的な材質は鋼管を採用。
尾翼は何と木製で、航空機黎明期に多く採用されていた羽布張りで補強している程度でした。
もちろん敵弾に耐えきれるわけがありませんが、観測も敵陣地の真上で見るわけじゃありませんから、制空権内限定での運用に絞ればこの程度でも問題なかったのでしょう。
制式採用には国産初のオートジャイロということもあって時間がかかってしまいましたが、昭和17年/1942年11月に試作機での審査が完了して採用と相成りました。
実際に国産の【カ号観測機】が誕生するのは実は昭和18年/1943年に入ってからなのですが、採用されたことからすぐに【カ号観測機】は発注されることになります。
昭和18年/1943年は60機、そして軌道に乗るであろう昭和19年/1944年には240機の製造が決定しました。
ちなみに【カ号観測機】の【カ】は萱場製作所の【カ】ではなく、「回転翼機」の【カ】です。
【テ号観測機】の【テ】は「低速固定翼機」の【テ】で、【テ号観測機】はだいたい【キ76/三式指揮連絡機】に近い存在です。
【カ号観測機】はアルグス・モトレン製のAs 10C空冷倒立V型8気筒エンジンを国産化させたエンジンを搭載していましたが、エンジンの過熱が酷いためにこのエンジンを採用した機体の製造は20機で打ち切られてしまいます。
【二型】からは試作機に使われていたジャコブスエンジンへと戻されて、以後は【二型】がどんどん生産される予定でした。
ところが当時はすでに【カ号観測機】が活躍できるような戦況とはかけ離れていました。
確かに「日華事変」では陸軍の支援のために【カ号観測機】の活躍の場は残されていたかもしれません。
しかし今や本格的な戦場は海を隔てた南洋の諸島群で、あまりに狭く、そしてジャングルの多い地域で【カ号観測機】の出番はありませんでした。
結局まだ使い道の残っていそうな中国大陸でも【カ号観測機】はほとんど使われることがなかったようです。
せっかく開発に成功したのに、【カ号観測機】は使われることなくお蔵入りになる寸前に陥ります。
しかしそこに救いの手を差し伸べたのは、またも意外な存在でした。
航空機を扱わない技術本部が航空機として【カ号観測機】を救い、今度は陸軍にとって全く埒外のエリアである海上での活躍の場を与えられたのです。
【カ号観測機】は揚陸艦からさらに護衛空母へと大変貌を遂げた【あきつ丸】の搭載機となり、着弾観測から対潜哨戒機としての方向転換をすることになりました。
事態は急を要し、6月に早速【あきつ丸】での【カ号観測機】の運用試験が行われました。
当時の【あきつ丸】には艦尾にデリックが搭載されていて、普通の艦載機のように艦尾から甲板に進入することができませんでしたが、そこは【カ号観測機】の性能を活かして左舷より進入して着艦に成功します。
もともと離発着距離が劇的に短いのが売りで、かつほとんど垂直に着艦できる【カ号観測機】でしたからこれぐらい造作もなかったでしょう。
さらに洋上での転舵中の着艦もすんなり成功し、ますます【カ号観測機】の期待は高まりました。
そしてこれを受けて早速搭乗員の訓練も始まりました。
確かに発着艦は問題ありませんが、【カ号観測機】の新任務は対潜哨戒ですから、これまで想定されていなかった「攻撃」という動きが必要になってきます。
潜水艦は基本的には浮上航行をしていますが、もちろん見つかるとすぐに潜航しますから、すぐさま攻撃に移らなければなりません。
最高速度は165km/hと、対潜哨戒機としては十分扱える速度ですが、急激な動きをする機体でもありませんから的確な攻撃態勢に入るのに時間がかかるのが問題でした。
それでも性能は対潜哨戒機にピッタリでしたから、訓練は厳しく行われました。
が、ここにきて思わぬ事態が発生します。
【カ号観測機】が全然生産されないのです。
なんとか働き口を見つけたというのに、肝心の機体がなければ何もできません。
すでに物資の不足が日本全体を取り巻いており、【カ号観測機】はその煽りを受けてしまったのです。
そんな中で急速に存在感を増してきたのが、やはり当初の目的とはかけ離れているものの、対潜哨戒機としての性能が認められた【三式指揮連絡機】でした。
低速、短距離での発着艦が可能、安定飛行ができる点は【カ号観測機】と同じです。
しかし【三式指揮連絡機】はそれに加えて、固定翼機であることから爆雷の搭載量を増すことができました。
さらに【三式指揮連絡機】は「見えすぎる」と言われるぐらいの広い視界があり、コックピットからの視界しかない【カ号観測機】に対して大きなアドバンテージとなりました。
そして何と言っても、もう数がそろっていること。
この結果、【あきつ丸】に搭載される哨戒機は【三式指揮連絡機】に取って代わられ、【カ号観測機】はまたも行き場を失ってしまいました。
結局【カ号観測機】は沿岸での対潜哨戒任務に仕方なく使われることになります。
ですが数がないのに配備と言われても、こんな特殊な機体のためにわざわざ人員も時間も割くほどの価値があったのかと言われるとはなはだ疑問です。
【カ号観測機】はこの陸上配備でも戦果を挙げた記録が残されておらず、敵機のやってこない地域へと退避を続けながら、細々と、ほんとに現地にいる人しかわかっていないぐらいの小規模で任務に就き続けました。
そんな状態でも、「ソロモン群島要地奪回作戦」の通称である「カ号作戦」と混同するからと言って昭和19年/1944年に【オ号観測機】へと改称されたりしています。
数えるほどしか配備されていない【カ号観測機】に対して、しかもこの圧倒的な劣勢の中で「カ号作戦」と混同するというのがよくわかりませんね。
そしてそもそも「カ号作戦」発令してるの昭和17年/1942年8月12日ですから、このタイミングでの改称の意図がますます不明です。
「オ号観測機」の【オ】は「オートジャイロ」の【オ】です。
総生産数は98機ですが、半分以上がエンジンなどの部品不足で未完成。
蓋を開けてみれば数種類あったSTOL機(Short Take Off and Landing/短距離離着陸機)の中でも、最も短距離離発着が可能であるにもかかわらず最も出番に恵まれなかった機体となってしまいました。
この時勢で【キ36/九八式直接協同偵察機】、【三式指揮連絡機】と3種類もSTOL機の開発に取り組んでいる点は、偵察と観測の思い入れが強すぎて1つに集中することができなかったという問題点を浮き彫りにしています。