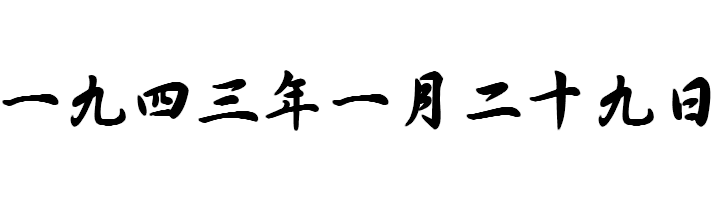| レンネル島沖海戦 | レンネル島海戦 |
戦闘参加戦力
| 大日本帝国 | 連合国 |
| 第一一航空艦隊(司令長官:草鹿任一中将) | 護衛部隊 |
| ・ラバウル基地部隊 | (司令官:ロバート・C・ギフェン少将) |
| 第七〇五航空隊(旧三沢航空隊) | 重巡洋艦【ウィチタ】 |
| 一式陸上攻撃機 16機 | 重巡洋艦【シカゴ】 |
| 第七〇一航空隊(旧美幌航空隊) | 重巡洋艦【ルイビル】 |
| 九六式陸上攻撃機 16機 | 軽巡洋艦【クリーブランド】 |
| ・カビエン基地部隊 | 軽巡洋艦【コロンビア】 |
| 第七五一航空隊(旧鹿屋航空隊) | 軽巡洋艦【モントピーリア】 |
| 一式陸上攻撃機 11機 | 駆逐艦【ラ・ヴァレット】 |
| 駆逐艦【シェヴァリエ】 | |
| 駆逐艦【コンウェイ】 | |
| 他駆逐艦数隻 |
ケ号作戦の大きな一助 ガ島奪還準備とアメリカ軍を錯覚させた海戦
1942年12月31日、太平洋戦争開戦から1年と半月がすぎ、「ミッドウェー海戦」に続く同戦争の大きな分水嶺が訪れた。
ガダルカナル島からの転進(撤退)が決定されたのである。
開戦前から日本が要所として挙げていた南方諸島の最東方の群島にあるガダルカナル島は、8月から陸海空で激しい戦闘が繰り広げられていた。
制空権を奪われてからの日本は苦しい戦いを強いられ、特に陸軍兵士達はアメリカ兵よりも飢えとの戦いに敗れて次々と斃れていった。
大晦日に大きな決断を下した日本は、ガダルカナル島に残る兵士たちを救出すべく、計画を練る。
これまで輸送をことごとく妨害され、多くの艦船が沈んでいる。
空もヘンダーソン飛行場の盤石な迎撃体制と「アクタン・ゼロ」後の【零式艦上戦闘機】の苦戦があり、生半可な計画では輸送艦が沈められたり、そもそも撤退作戦そのものが露呈しかねない。
日本はアメリカに対し、戦力の増強と徹底抗戦の構えがあるように誤認させる必要があった。
1943年1月、「ガダルカナル島撤収作戦(ケ号作戦)」の前準備として、一時中断していた鼠輸送を再開し、また撤退決定の直前から潜水艦の輸送も再開した。
一方で1月15日からはガダルカナル島やポートモレスビー、ラビへの攻撃を強化し、輸送再開と攻撃激化から、アメリカに日本の戦闘意欲に衰えがないことを突きつけた。
しかし激化したからと言って、日本が優位に立てるわけではない。
飛行場への陸海共同の航空撃滅戦を始め、敵基地や航空機との戦闘では大きな被害を負っている。
1月29日、日本の偵察機がガダルカナル島の南東に位置するサンクリストバル島(現マキラ島)の南海上を航行する輸送艦隊を発見した。
幸いこちらは艦隊には気づかれた様子はない。
偵察機は直ちに報告し、各航空基地からそれぞれ到達時刻を日没頃に調整して【九六式陸上攻撃機、一式陸上攻撃機】が発進した(機数が複数資料ありのため不明)。
報告によると、輸送艦隊は輸送用の護衛空母2隻と重巡洋艦・軽巡洋艦各3隻ずつ、駆逐艦8隻というなかなかの規模の艦隊であった。
これはガダルカナル島への輸送艦隊で、現地の兵士の交代要員を載せてガダルカナル島へ向かっていたのである。
指揮官であるロバート・C・ギフェン少将はこの輸送が太平洋戦争での初任務であった。
第二次世界大戦の「トーチ作戦」(北アフリカ戦線の制圧作戦)に参加していたが、作戦の成功の目処がたったため、太平洋戦線へ転属となった。
太平洋の大海原で、18ノットという護衛空母の低速によって艦隊のスケジュールは狂い始めていた。
そして19時頃に所定の場所で現地で哨戒を続けている駆逐艦4隻と合流予定だったが、これに間に合わないとわかると護衛空母は2隻の駆逐艦を護衛につけて、艦隊から分離させた。
護衛艦が減るのは危険ではあるが、もともとこの近海はアメリカが実質支配している海域であるし、制空権も保てているので問題ないという判断だったのだろう。
索敵機の情報から陸攻は一直線に艦隊を目指した。
しかし天候は悪く、加えて到着は日が沈むか沈まないかという時間帯だ。
やむなく高度を下げて飛行を続けていると、ついに雲間から艦隊の航跡を発見。
艦隊はまだこちらに気づいた様子はない。
17時19分、地平線にわずかに日が見える頃、先に到着した第七〇五航空隊が艦隊に突撃した。
しかしアメリカ艦の機銃の豊富さは奇襲にも動じない。
発見後、すぐさま風防の目の前には無数の黒点が広がり、夥しい数の対空機銃と高角砲が第七〇五航空隊を襲った。
決死の雷撃を行うも命中はなく、逆に【一式陸攻】が1機撃墜された。
やがて日も沈み、あたりは薄暗くなってきた。
続いて第七〇一航空隊が第二次攻撃を開始。
7機は照明弾を落とす役割を担っており、暗がりでも艦隊は白日のもとに晒された。
しかし艦隊は陸攻の接近を許さない。
またも1機が撃墜され、暗夜に一筋の炎が横切っていく。
その撃墜された【一式陸攻】の操縦桿を握っていた第七〇一航空隊飛行長の檜貝嚢治少佐の目は、操縦桿ではなく1隻の巡洋艦を捉えていた。
【ノーザンプトン級重巡洋艦 シカゴ】
この洋上、この時間、海上に突っ込んでも、もしその瞬間は生きることができても助かるわけがない。
鱶の餌になるよりも、この身果てるまで国へ奉仕するのが日本男児。
檜貝機の炎は【シカゴ】に向かって隕石のように落下していった。
瞬間、【シカゴ】で大爆発が起こる。
檜貝機の壮絶な自爆により、【シカゴ】は炎上し、そして彼が身を挺して作り出した闇夜の巨大な松明に向けて陸攻は殺到した。
見事2本の魚雷が【シカゴ】に命中。
また【ノーザンプトン級重巡洋艦 ルイビル】【重巡洋艦 ウィチタ】にも1本ずつの魚雷が命中したが、残念ながらいずれも不発であった。
そして【シカゴ】もまた、健在だった。
2発の魚雷を受けて航行はできなかったが、陸攻が去った後、【ルイビル】に曳航されて艦隊は再び目的地へ向けて出発した。
しかし日本の攻撃はこれだけではなかった。
翌30日、ブカ島から第七五一航空隊が発進し、また近海で活動していた【伊17、伊25、伊26、伊176】も支援に向かう。
14時6分、無事航空隊は再び輸送艦隊を発見する。
曳航されている【シカゴ】もはっきり見えた。
この時曳航艦は曳船【ナバホ】へ変更されていた。
殺到する航空隊に対してまたも網のような弾幕が襲いかかる。
しかも29日にはなかった思わぬ障壁が航空隊に立ちふさがった。
【ヨークタウン級航空母艦 エンタープライズ】直掩機の襲来である。
実はこの輸送艦隊の後方にはずっと【エンタープライズ】と【サラトガ】を中心とした護衛艦隊が存在したのである。
29日の奇襲の際は現れなかったが、この襲撃を受けて予め護衛機を飛ばしていたのだ。
そして日本の索敵機も、この護衛艦隊の存在には気づいていなかった。
苛烈を極める対空砲火と、戦闘機からの攻撃を浴びながらも、止めを刺さんと【シカゴ】には次々と陸攻が迫ってきた。
しかし日本側には戦闘機がいない。
防御力が乏しい陸攻は次々と火を噴き始めた。
ここが我らの死に場所である、操縦桿を握るパイロットは命を賭して米艦隊に魚雷を放ち続けた。
11機中7機が撃墜されたが、【シカゴ】には新たに4本の魚雷を叩き込んだ。
ここまで耐えきった【シカゴ】もこの猛襲には為す術なく、沈没した。
また、【フレッチャー級駆逐艦 ラ・ヴァレット】にも魚雷1本が直撃し大破させている。
少ない航空戦力を10機失ったのは大きいが、「レンネル島沖海戦」は戦果以上の効果があったのは間違いない。
敵の目をかいくぐって艦隊に奇襲を仕掛ける好戦的な日本のどこに撤退の気配があろうか。
アメリカは警戒をより厳しくし、ガダルカナル島での戦いに向けてさらなる作戦の立案や兵力の増強を模索していく。
その必要はもはやないというのに。
そして2月1日、ついに「ガダルカナル島撤収作戦」が開始される。
一方で、アメリカは単なる重巡1隻の沈没では済まされない事態に直面していた。
【シカゴ】には超秘密兵器「VT信管(近接信管)」が搭載されていたのである。
「マリアナ沖海戦」で有名な「VT信管」であるが、この時からすでに兵器としては一応完成しており、1月に【セントルイス級軽巡洋艦 ヘレナ】が試作機として使用した近接信管弾で【九九式艦上爆撃機】の撃墜に成功している。
【シカゴ】でも同様に試験的に搭載されたのだが、結果が航空機による雷撃で沈没という、最悪なものとなった。
言わずもがな、「VT信管」は放出された電波が目標に当たった際の周波数の変移を起爆スイッチとする、直撃しなくても至近距離で爆発する兵器である。
その兵器がありながら、敵機に接近されて計6本もの雷撃を受けたというのは、とても公にできるものではなかった。
太平洋艦隊司令長官であったチェスター・ミニッツ大将はこの沈没の事実を決して軍外部に漏らさないように要請している。
長年に渡って多額の研究費をかけて開発した結果が「効果はありません」では示しがつかない上、軍人たちもこの兵器に不信感を抱くことになる。
再び「VT信管」は改良を進められ、徐々に各艦に配備が進むようになったが、それでも1944年6月の「マリアナ沖海戦」では万全の体制とまではいかず、全高角砲弾のうち近接信管弾は2割程度しか配備が間に合っていない。
| 日本の勝利 |
両者損害
| 大日本帝国 | 連合国 |
| 沈 没 |
| 【シカゴ】 |
| 大 破 |
| 【ラ・ヴァレット】 |
| 喪 失・損 傷 |
| 一式陸上攻撃機 10機 喪失 |