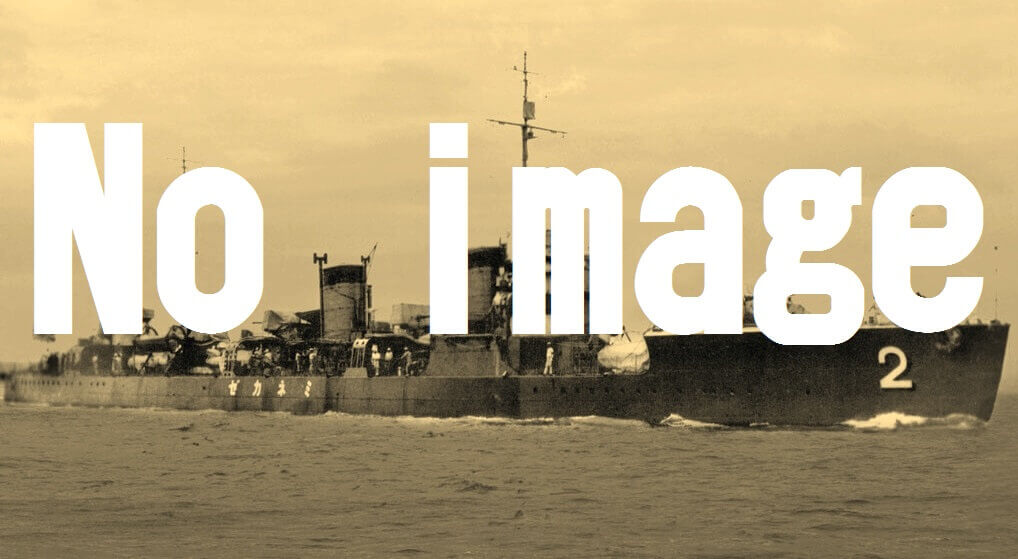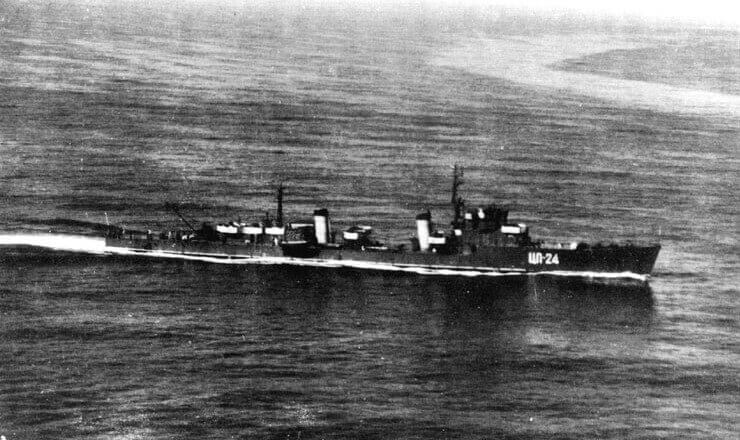| 起工日 | 昭和19年/1944年9月1日 |
| 進水日 | 昭和20年/1945年1月17日 |
| 竣工日 | 昭和20年/1945年3月15日 |
| 退役日 (沈没) |
昭和23年/1945年7月28日 |
| 平群島 | |
| 建 造 | 川崎造船所 |
| 基準排水量 | 1,289t |
| 垂線間長 | 92.15m |
| 全 幅 | 9.35m |
| 最大速度 | 27.3ノット |
| 航続距離 | 18ノット:3,500海里 |
| 馬 力 | 19,000馬力 |
| 主 砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |
| 40口径12.7cm単装高角砲 1基1門 | |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 |
| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |
| 25mm単装機銃 12基12挺 | |
| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 2基 |
| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |
一度沈みながらも、再び海原を駆け巡ることができた梨
【梨】は日本の海軍史上でも非常に稀有な存在です。
【梨】は帝国海軍所属の戦闘艦艇としては唯一、海上自衛隊に所属することができた船なのです。
ちなみに掃海艇や特務艦を含めると少数ですが他にも存在します。
さて【梨】ですが、3月15日に第十一水雷戦隊に配属され、他の艦同様瀬戸内海で訓練を行っていました。
【梨】は4月6日に発動した「天一号作戦」に当初は参加予定でしたが、これは中止となり、その後山口県八島へ移動します。
5月20日は【萩】とともに第三十一戦隊、第五十二駆逐隊に編入、また同時に「回天」突撃部隊とも言える海上挺進部隊にも所属することになりました。
7月からは自身も「回天」搭載艦へと改装され、「回天」の基地がある平生へ移します。
燃料不足が叫ばれる中、悲しいかな「回天」を背負う【梨】と【萩】にはまだ優先的に燃料が回され、他の船は偽装係留されて戦力温存が図られます。
7月E8日、【梨】は平郡島沖で停泊していたところをアメリカ軍に急襲されます。
この時攻撃を仕掛けてきたのは【F6F】。
朝から昼にかけてひっきりなしにやってくるアメリカ軍の攻撃に翻弄された【梨】は、何発ものロケット弾を被弾します。
そのうちの1発のロケット弾は甲板をを貫通して後部の船倉で爆撃し、この衝撃で舷側から艦底に穴が開いて浸水が始まりました。
さらに推進軸も変形し、その軸の付け根も穴が開いて、そこからも海水が入り込んでしまいます。
一切の手加減がない爆撃で、今度は左舷第一缶室付近に至近弾を浴び、ここでも破孔から浸水が発生して【梨】はどんどん海に引きずり込まれます。
結局その被害に耐えきれずに【梨】はついに沈没。
死者と行方不明は合わせて60名にのぼりました。
時を進めて昭和19年/1954年。
「朝鮮戦争」による特需などもあり、日本は焼け野原になった国土から急速に回復を続けていました。
まだ一般社会への恩恵は乏しかったものの、失われていた日本の力が徐々に復活の兆しを見せ始めます。
(アメリカへ支払う様々な名目のお金が膨大に必要だったため、国家財政としてはまだまだ火の車です。)
そんな中、日本は需要が高い鋼材の確保に動いていました。
旧帝国海軍の船の解体はほとんど終わっていたため、新しいスクラップを探さなければなりません。
そこで浮上してきたのが、瀬戸内海の比較的浅い場所に沈んでいた【梨】でした。
9月21日、浮揚された【梨】は10年ぶりにその姿を現しました。
そしてその姿は、9年間海中に没していたとは思えないほど、航行当時のままだったそうです。
調査の結果も良好で、スクラップどころか船本来の力すら発揮できるほどだった(機器類は当然修理や交換前提です)【梨】は、本当に船としての再利用の議論が沸き起こりました。
しかし再利用できるとはいっても、もともとの用途から【梨】はすでにスクラップ用として民間へ払い下げられていたので、改装だけでなくその船を再度買収するコストもかかってきます。
それにもかかわらず当時の防衛庁が【梨】復活を目指したのは、一説には「海上自衛隊は日本の海を守り続けてきた帝国海軍の意思を受け継ぐものである」ということを証明したかった、とも言われています。
そして【梨】は正式に国が買い上げることになったのですが、このような経緯もあり、国会では野党に厳しく追求を受け続けました。
護衛艦 わかば/Destroyer WAKABA
| 浮揚日 | 昭和29年/1954年9月21日 |
| 就役日 | 昭和31年/1956年5月31日 |
| 再就役日 | 昭和33年/1958年3月26日 |
| 退役日 (除籍) |
昭和46年/1971年3月31日 |
| 修 復 | 呉造船所 |
| 基準排水量 | 1,250t |
| 全 長 | 100.0m |
| 全 幅 | 9.35m |
| 最大速度 | 25.5ノット |
| 航続距離 | 16ノット:4,680海里 |
| 馬 力 | 15,000馬力 |
| 主 砲(2次改装) | Mk.33 Mod0 50口径3インチ連装砲 1基2門 |
| 魚 雷(5次改装) | 65式533mm連装魚雷発射管 1基4門 |
| レーダー | AN/SPS-12対空レーダー(2次改装) Mk.34射撃レーダー(2次改装) US SO水上レーダー(2次改装) SPS-5B水上レーダー(2次改装) AN/SPS-8B高角測定レーダー(3次改装・ 6次改装時撤去) Mk.63 Mod11射撃式装置(2次改装) |
| ソナー | SQS-11A捜索用ソナー(3次改装) SQR-4/SQA-4探査用ソナー(3次改装) T-3国産試作ソナー(4次改装) |
| その他 | 54式対潜弾発射機 1基(2次改装) 54式爆雷投射機 4基(2次改装) 54式爆雷投下軌条 2条(2次改装) |
一悶着ありましたが、【梨】は昭和31年/1956年5月31日、修理と改装を経てついに復活の時を迎えます。
名は【警備艦 わかば】とされ、最初は主に練習艦運用を求められます。
【わかば】とされた理由は、まず海上自衛隊は艦名をひらがなにすることになっていますが、「なし」では「無し」と思われてしまいます。
そのため、かつて「松型、橘型」での命名の慣例とされた草木に関する言葉から、未来を担うというポジティブな意味も込めて【わかば】という名が採用されました。
しかし【わかば】は復活当初から悩みの種だらけでした
何しろ9年も海水に浸かっていたわけですから、いくら修理したとしてもなかなか快調に機関は動いてくれません。
けたたましい異音が【わかば】から発せられ、ろくに会話もできないほどだったそうです。
また、旧式でしかも戦時急造機構の【わかば】に類する艦船は他に存在しませんでした。
運用でも修理も参考にできる船がないため、管理に大変苦労したようです。
そしてさらに月日は流れて、【わかば】は第二次改裁を受けることになりました。
この時にはAN/SPS-12対空レーダーや50口径3インチ連装砲をはじめとした、アメリカ式の武裁がしっかりと施されています。
そして昭和33年/1958年3月26日、今度は【乙型警備艦 わかば】として再就役します。
しかし警備艦とは言うものの、【わかば】はもっぱら兵装実験艦としての任務を行うことになります。
「乙型」として再就役した時には主砲やレーダー、対潜ソナー等の標準的な装備を揃えていましたが、昭和43年/1968年からは実用実験隊に編入され、ますますその毛色が色濃くなりました。
ソナーは次々に入れ替わり、レーダーはAN/SPS-8B高角測定レーダーを後に採用。
特にこの高角測定レーダーは、海上自衛隊で唯一装備した艦となっています。
その他にも数年おきに武裁や機器類の変更が行われ、実験艦らしく【わかば】の装備はとっかえひっかえでした。
【わかば】には旧【梨】の乗員が優先的にあてがわれました。
上記のように同型艦がいないため、運用のためにもかつての乗員というのはとても貴重な存在でした。
しかし一方で幽霊騒ぎが後を絶たなかったという話もあります。
同艦でも死人が当然出ていて、船は一度海没、そしてその時の乗員は長い間船を枕に眠っていたわけですから、幽霊が出そうな条件は確かに整っていたように思います。
あまり実践としての活動をしなかった【わかば】ですが、昭和37年/1962年には三宅島で大噴火がありました。
その時【わかば】は住民の避難のために三宅島へ向かい、無事に住民を東京まで送り届けています。
しかし退役1年前の昭和45年/1970年には訓練中に小型タンカーと衝突するという事故も起こってしまいました。
そして昭和46年/1971年、数々の実験を行ってきた【わかば】にもついに最後の時がやってきます。
3月31日、復活してから15年、【梨】として竣工してから26年目。
【わかば】はこの日を持って除籍され、波乱の艦生を閉じました。
しばらくは保管されていましたが、昭和50年/1975年に古沢鋼材へ売却され、そこで丁寧に解体されました。