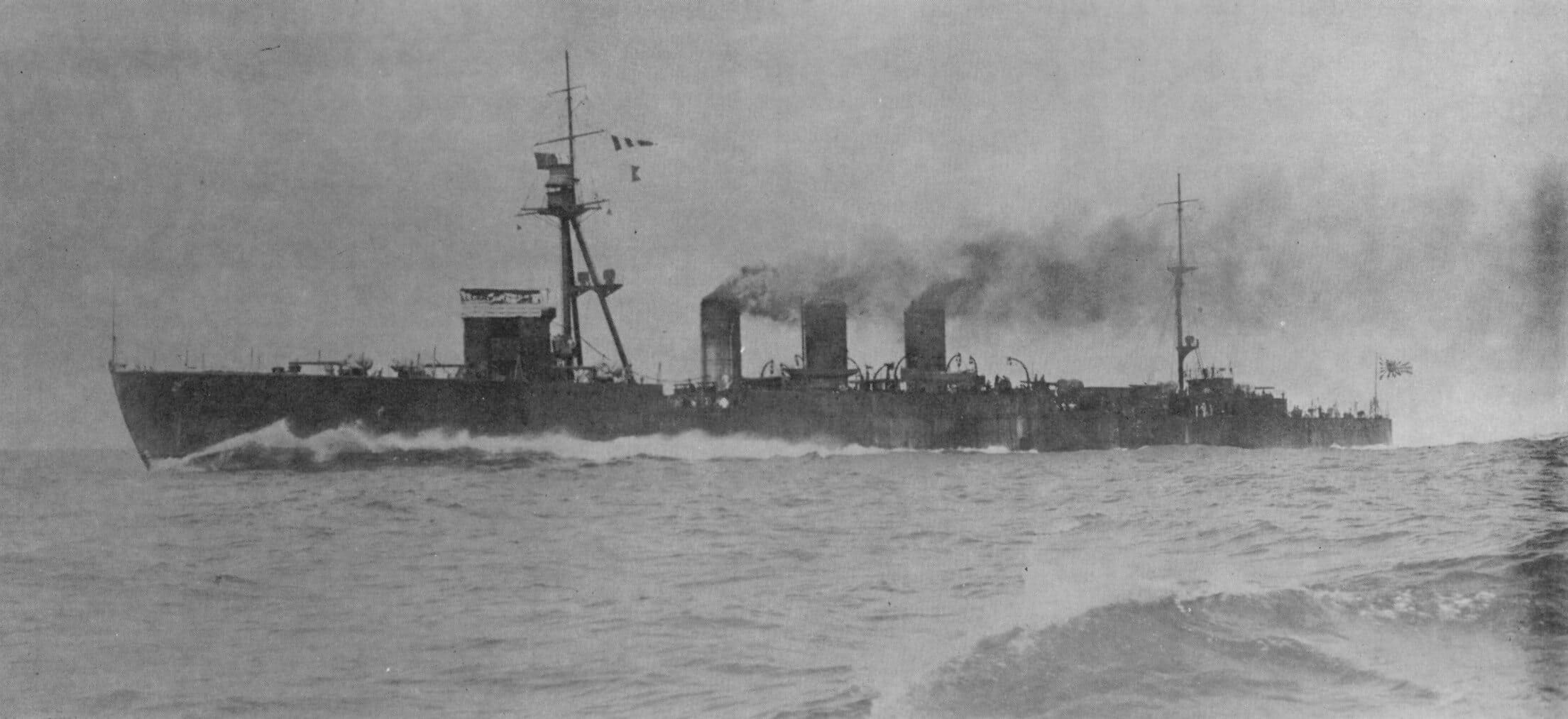 軽巡洋艦
軽巡洋艦球磨型
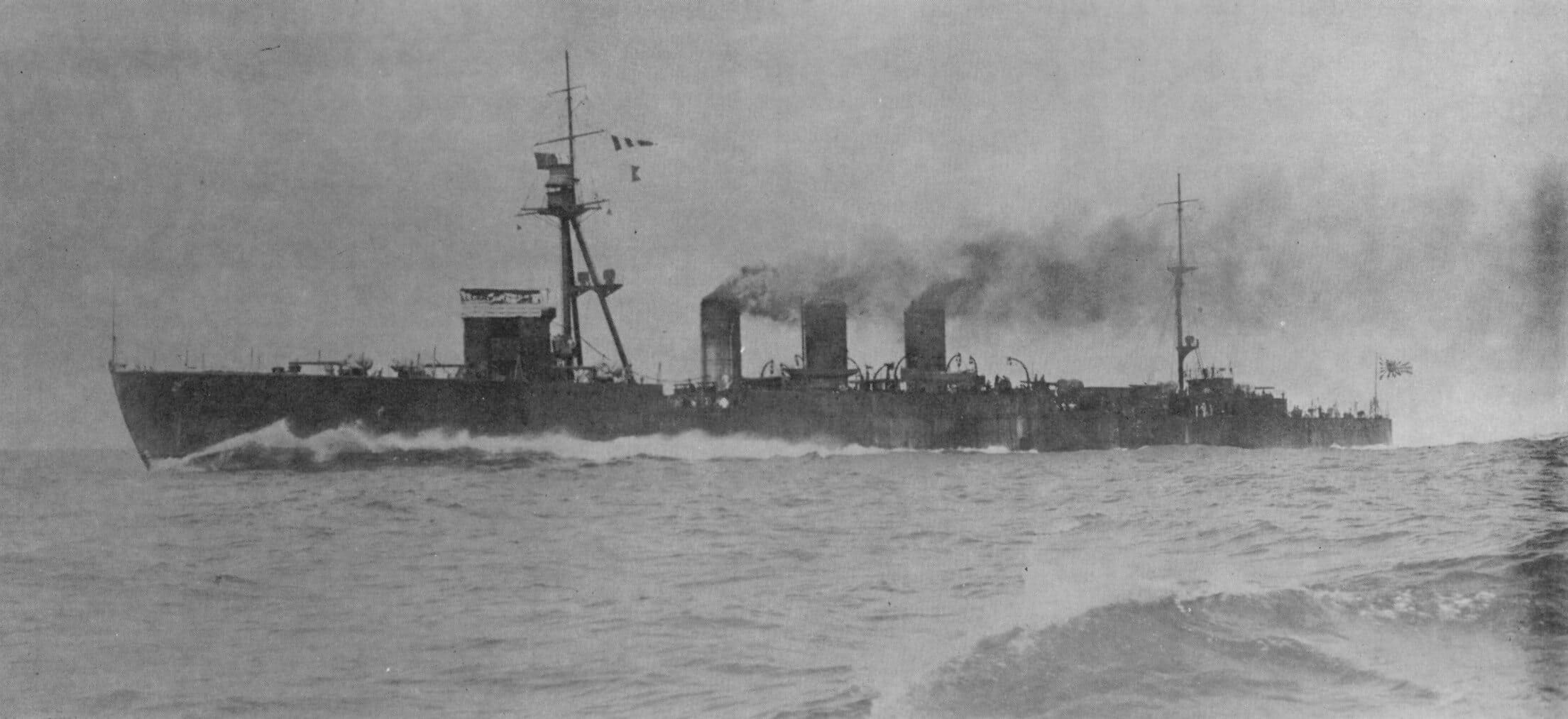 軽巡洋艦
軽巡洋艦『球磨型軽巡洋艦』
 軽巡洋艦
軽巡洋艦帝国海軍巡洋艦の進化 その2
Evolution of IJN heavy cruiser No.2
 軽巡洋艦
軽巡洋艦木曾【球磨型軽巡洋艦 五番艦】
【Kuma-class light cruiser fifth】
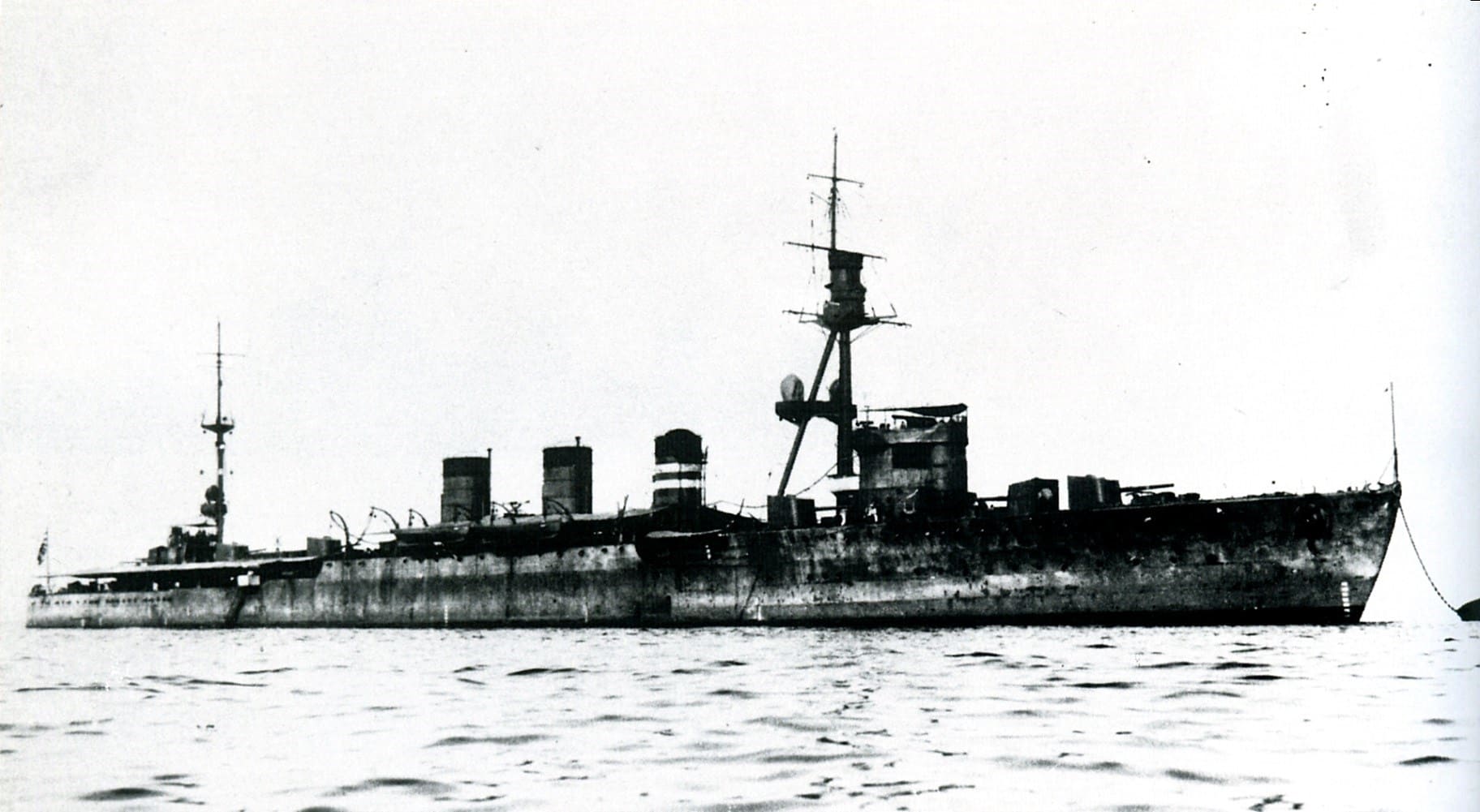 軽巡洋艦
軽巡洋艦大井【球磨型軽巡洋艦 四番艦】
【Kuma-class light cruiser forth】
 軽巡洋艦
軽巡洋艦回天搭載艦 北上【球磨型軽巡洋艦 三番艦】
【Kuma-class light cruiser third KAITEN carrier】
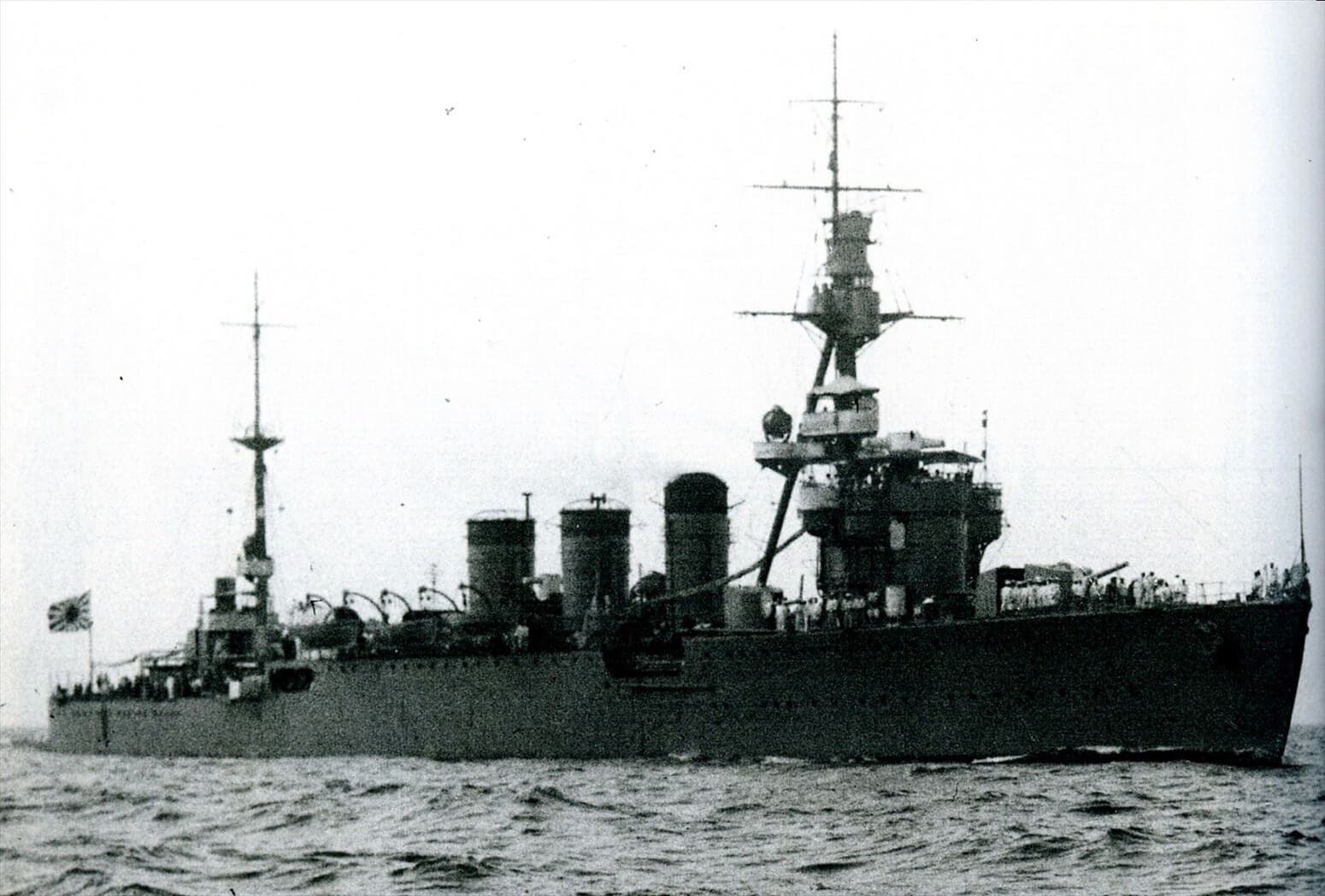 軽巡洋艦
軽巡洋艦北上【球磨型軽巡洋艦 三番艦】
【Kuma-class light cruiser third】
 軽巡洋艦
軽巡洋艦多摩【球磨型軽巡洋艦 二番艦】
【Kuma-class light cruiser second】
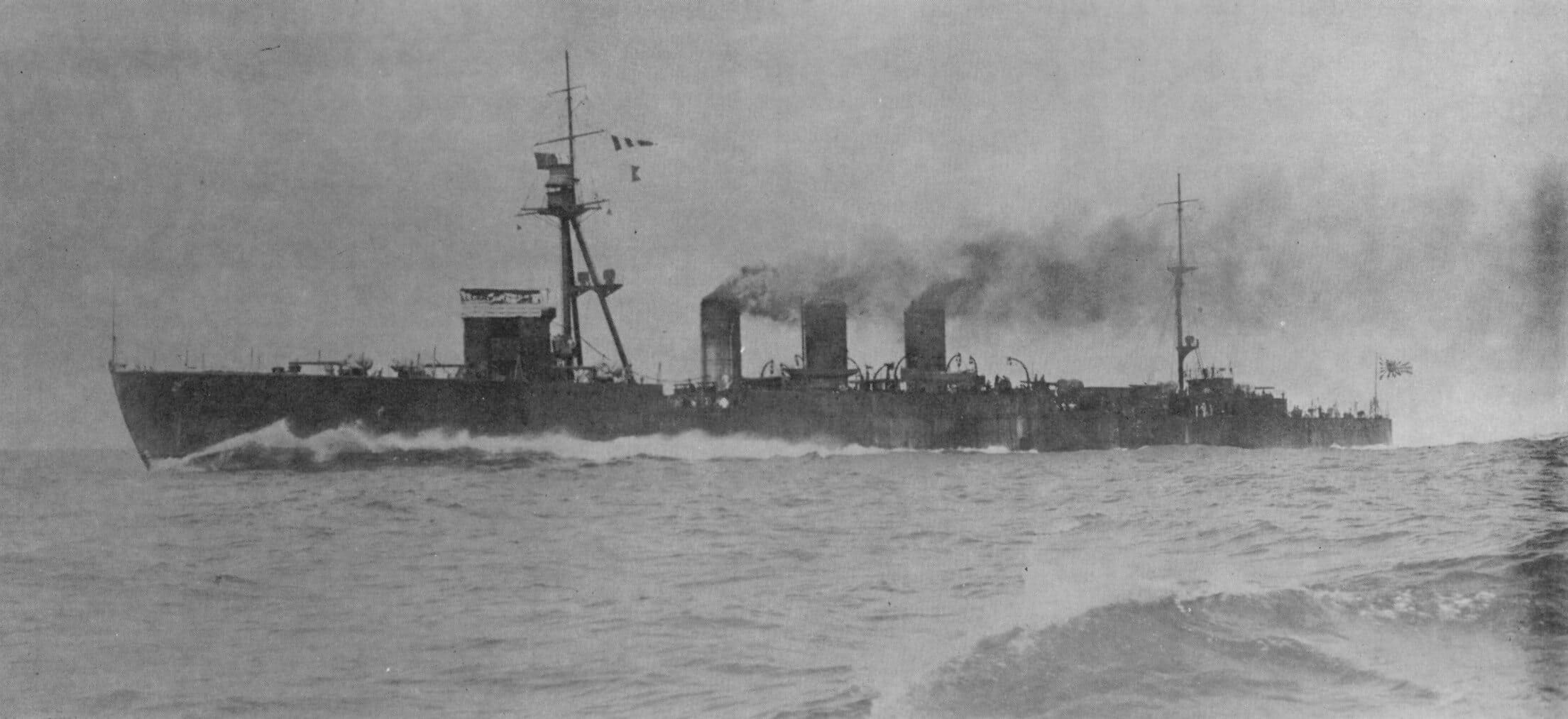 軽巡洋艦
軽巡洋艦