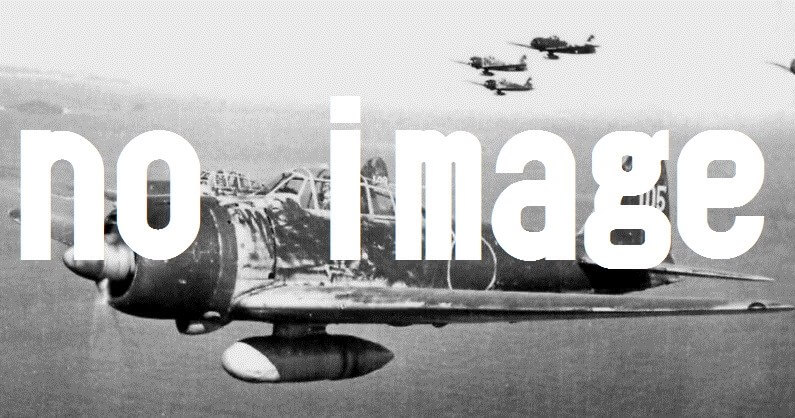| 零戦開発物語 | 零戦と戦った戦闘機達 |
| 零戦+防弾性-Xのif考察 | 零戦と防弾性の葛藤 |
大前提として、型式の付番パターンを説明しておきます。
型式は2桁の数字で構成されますが、10の桁の数字が機体形状、1の桁の数字がエンジン型式を表します。
【三二型】の次が【二二型】になるのは、生産された順番ではなく、【二一型】の機体形状に【三二型】のエンジンが搭載されたためです。
零式艦上戦闘機四一型
※すべて推定値です
| 全 長 | 9.050m |
| 全 幅 | 11.000m |
| 全高(三点) | 3.570m |
| 主翼面積 | 22.438㎡ |
| 翼面荷重 | |
| 自 重 | |
| 正規全備重量 | |
| 航続距離 | |
| 発動機/離昇馬力 | 栄一二型/940馬力 |
| 上昇時間 | |
| 最大速度 | |
| 急降下制限速度 | 629km/h |
| 燃 料 | |
| 武装/1挺あたり弾数 | 九七式7.7mm機銃 2挺/700発 九九式20mm機銃一号もしくは二号四型 2挺/125発 |
| 搭載可能爆弾 | 30kgもしくは60kg爆弾 2発 |
| 符 号 | |
| 生産数 | 計画のみ |
出典:
[歴史群像 太平洋戦史シリーズVol.33]零式艦上戦闘機2 学習研究社 2001年
歴史的には表舞台に出ることがなかった【四一型】および【四二型】。
表舞台どころか存在すらあやふやなこの2機種ですが、結局存在したのでしょうか、またそれはどのようなものだったのでしょうか。
まず【四一型】がどこから現れたかと言うと、元になるのは【二一型】です。
【零戦】の20mm機銃はドラム×60発から最後はベルト×125発まで段階的にグレードアップしていきましたが、【四一型】は【二一型】にベルト式給弾100~150発の20mm機銃(現実だと九九式二〇粍一号もしくは二号機銃四型に相当)を搭載した場合の仮称でした。
ベルト式が実際に搭載されたのは昭和19年/1944年3月から生産が始まった【五二甲型】からですが、この【四一型】が検討されたのは前年4月とほぼ1年前です。
【四一型】は【二一型】に専念していた中島だけに発注する予定だったようで、このことからも【二一型】の純粋後継機扱いを考えていたタイプであることがわかります。
また同時に、【二二型】の20mm機銃をベルト式にし、さらに翼端を【三二型】のように再び50cm短くするタイプとして【五二型】の仮称が与えられた案が登場しています。
つまり昭和18年/1943年時点で【零戦】には【二一型】→【四一型】と【二二型】→【五二型】の2パターンに分類されることになったわけです。
【五一型】ではなく【五二型】なのは付番の法則からもわかります。
ですが【四一型】は九九式二〇粍二号機銃四型の開発が遅れてしまい、開発は中止。
書類上の存在で終わってしまいました。
【五二乙型】などがあるのでこれも【二二乙型】でもいいんじゃないかという疑問については、そもそも「乙」以下を型式名称に取り入れることが決まったのが昭和19年/1944年10月の「航空機名称付与様式」の改定後からとのことですので、【四一型】の時には当てはまらないようです。
じゃあ【五二乙型】は間に合ったのかと言うと、生産開始は昭和19年/1944年6月からですが制式採用が10月なので、「乙」表記のために改訂されたものだと考えていいでしょう。