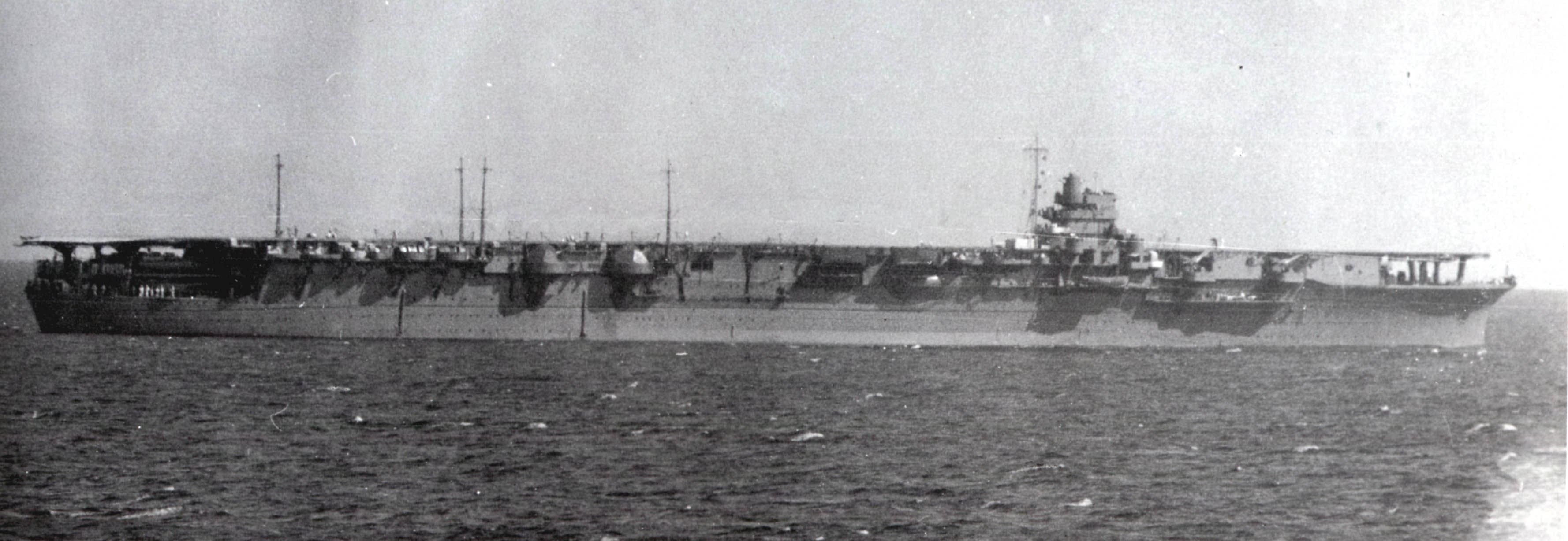 航空母艦
航空母艦マリアナ沖海戦
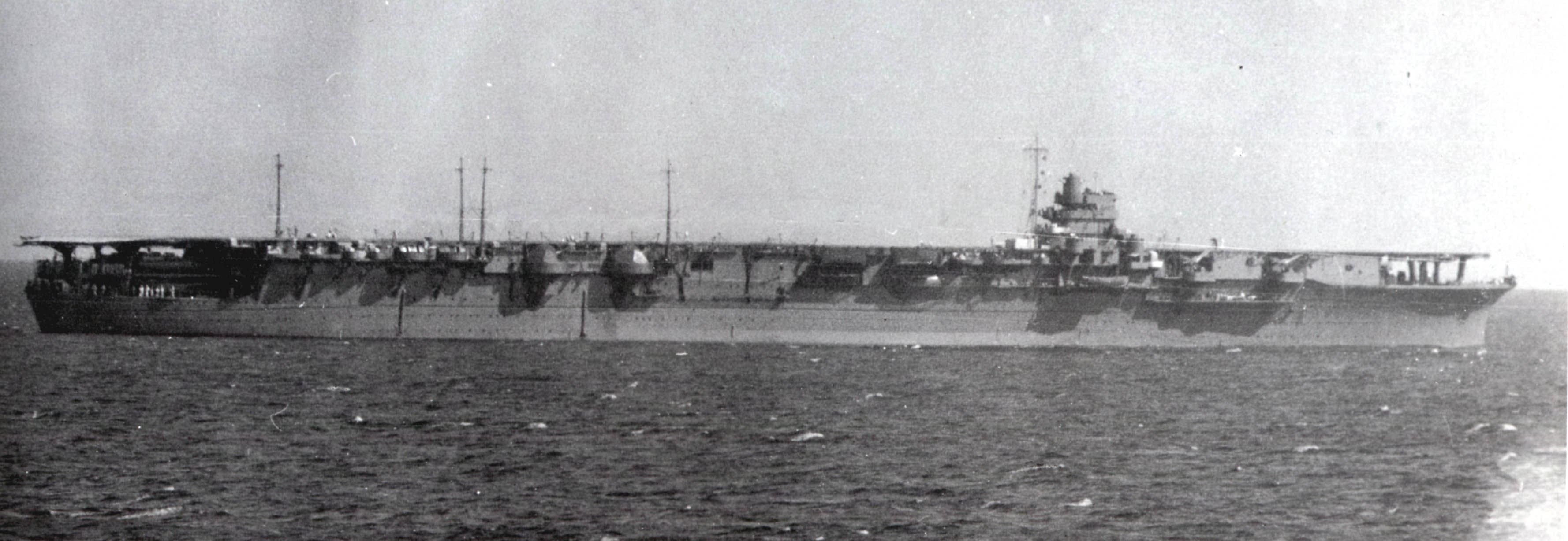 航空母艦
航空母艦瑞鶴【翔鶴型航空母艦 二番艦】その3
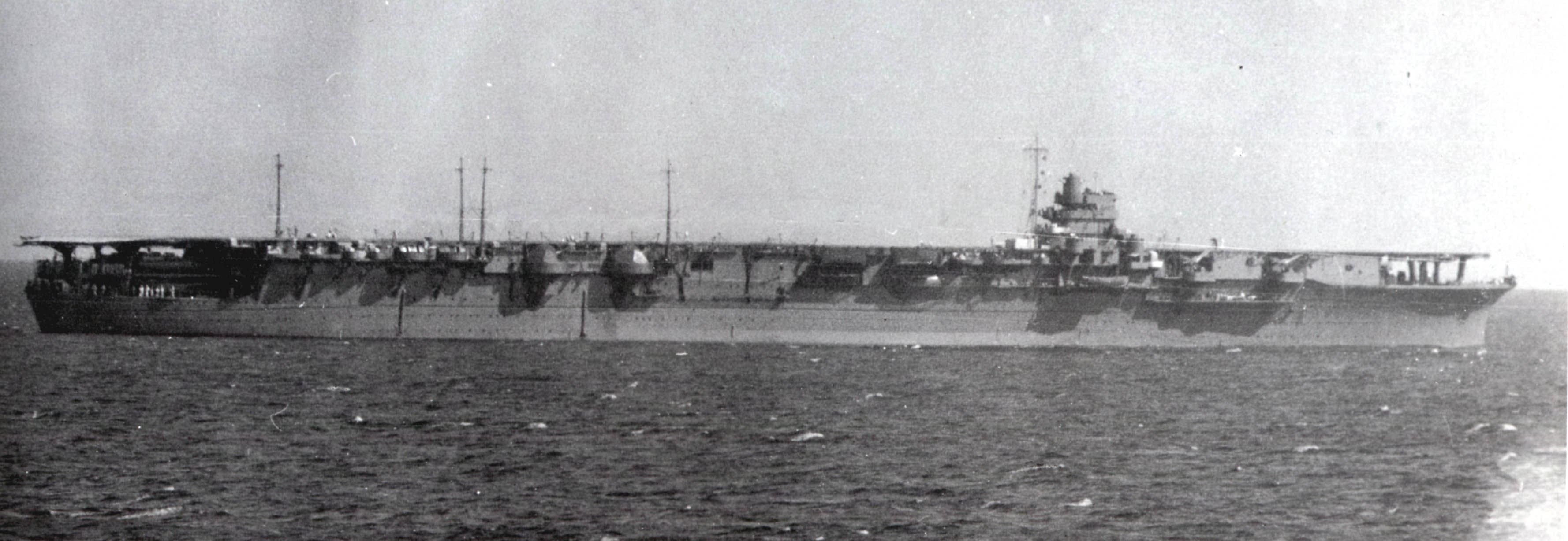 航空母艦
航空母艦瑞鶴【翔鶴型航空母艦 二番艦】その2
Zuikaku【Shokaku-class aircraft carrier Second】
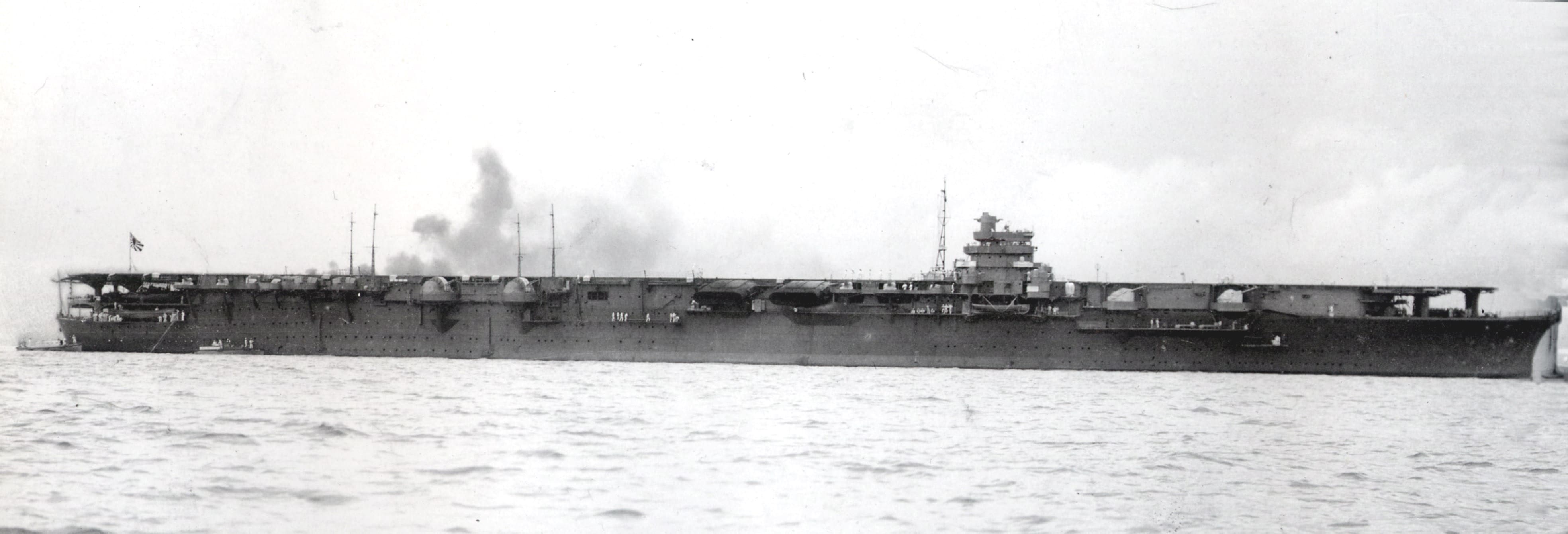 航空母艦
航空母艦翔鶴【翔鶴型航空母艦 一番艦】その4
Shokaku【Shokaku-class aircraft carrier First】
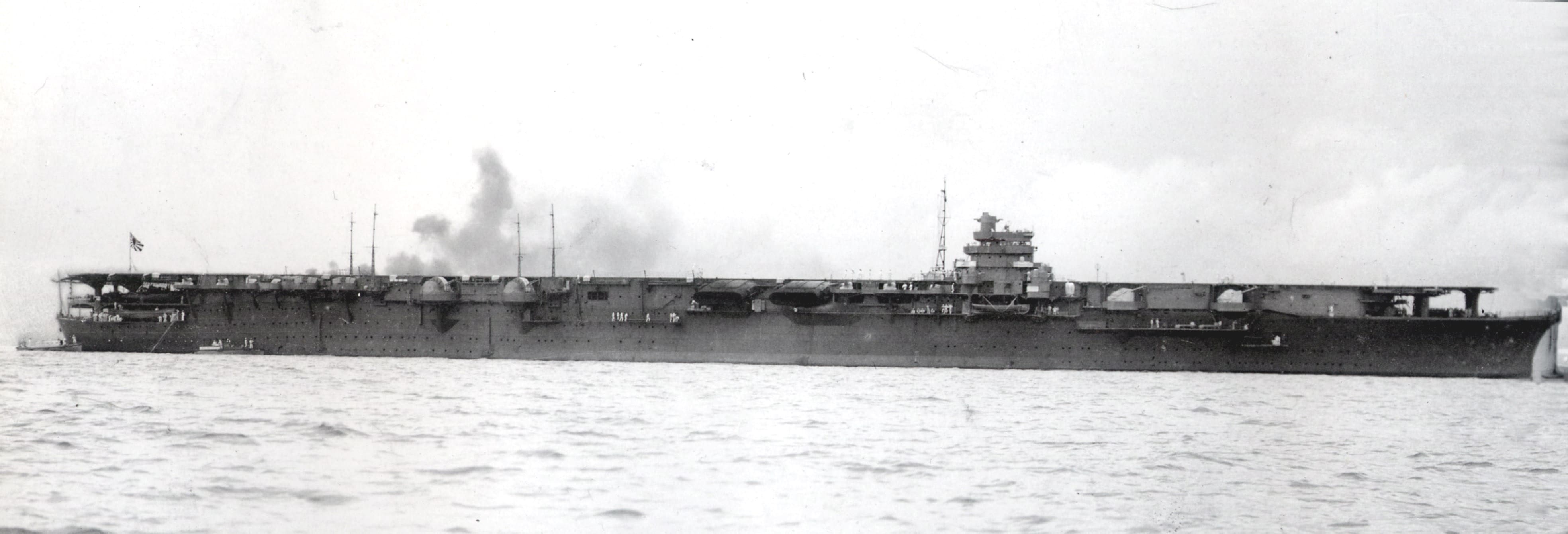 航空母艦
航空母艦翔鶴【翔鶴型航空母艦 一番艦】その3
Shokaku【Shokaku-class aircraft carrier First】
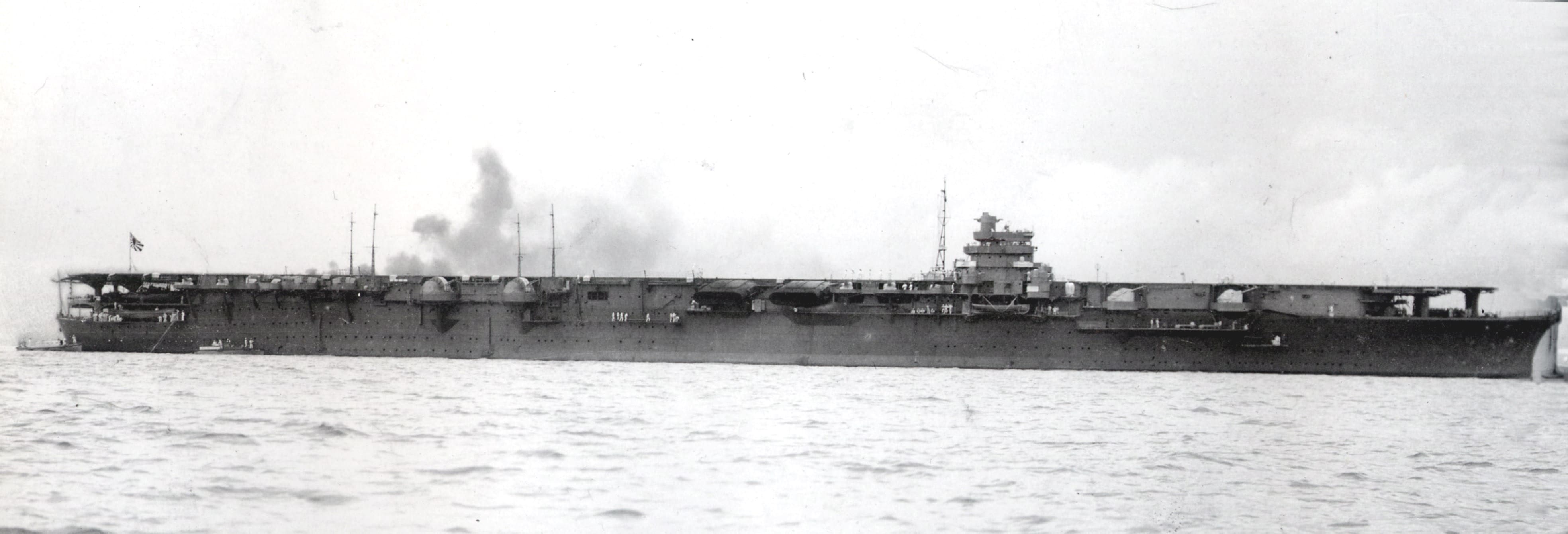 航空母艦
航空母艦翔鶴【翔鶴型航空母艦 一番艦】その2
Shokaku【Shokaku-class aircraft carrier First】
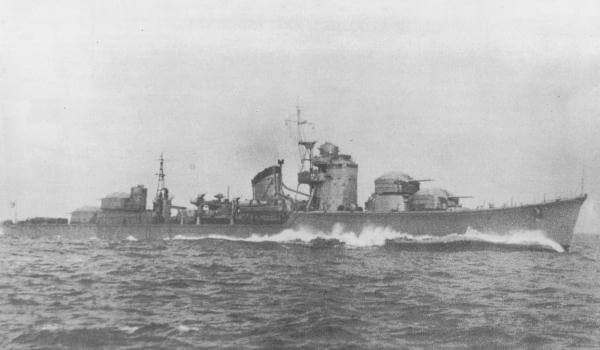 駆逐艦
駆逐艦初月【秋月型駆逐艦 四番艦】その2
Hatsuzuki【Akizuki-class destroyer】
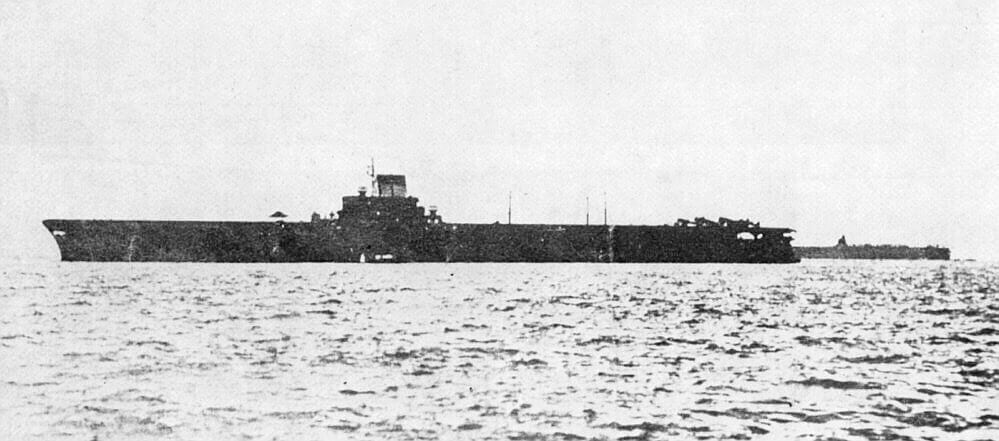 航空母艦
航空母艦大鳳【航空母艦】その2
Taiho【aircraft carrier】
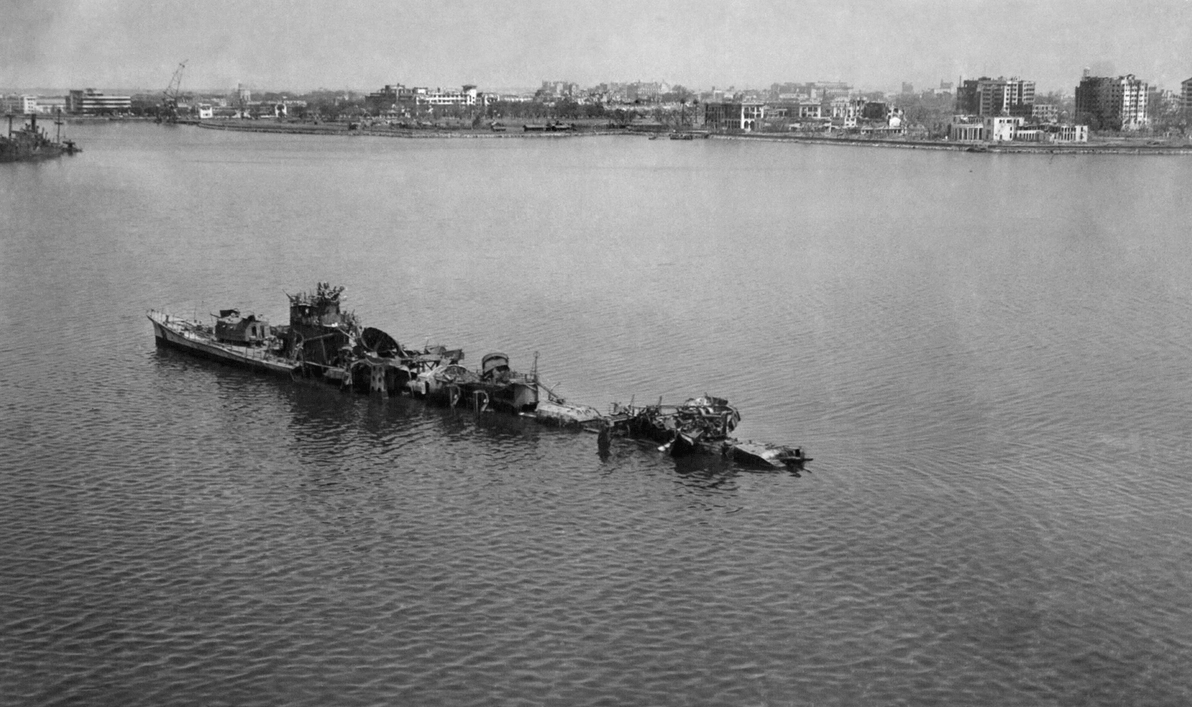 駆逐艦
駆逐艦沖波【夕雲型駆逐艦 十四番艦】その2
Okinami【Yugumo-class destroyer】
 駆逐艦
駆逐艦長波【夕雲型駆逐艦 四番艦】その3
Naganami【Yugumo-class destroyer】
 駆逐艦
駆逐艦