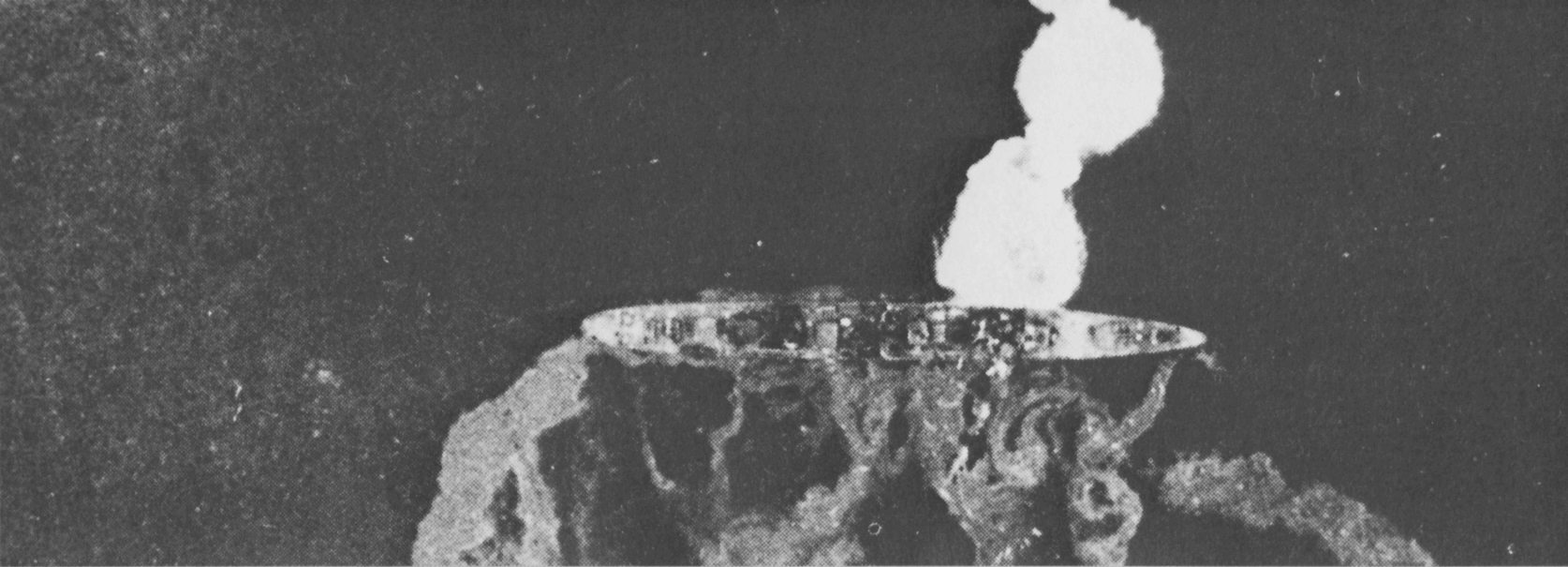| 起工日 | 昭和10年/1935年9月7日 |
| 進水日 | 昭和11年/1936年12月16日 |
| 竣工日 | 昭和12年/1937年8月31日 |
| 退役日 (沈没) | 昭和18年/1943年3月3日 |
| ビスマルク海海戦 | |
| 建 造 | 佐世保海軍工廠 |
| 基準排水量 | 1,961t |
| 垂線間長 | 111.00m |
| 全 幅 | 10.35m |
| 最大速度 | 35.0ノット |
| 航続距離 | 18ノット:3,800海里 |
| 馬 力 | 50,000馬力 |
| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 3基6門 |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |
| 次発装填装置 | |
| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |
| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |
| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |
勇猛果敢に敵に挑んだ、義理堅い駆逐艦
【朝潮】は【大潮】【満潮】【荒潮】とともに第八駆逐隊を編成し、「マレー作戦、リンガエン湾上陸作戦」に従事。
昭和17年/1942年2月からは「バリ島攻略作戦」に参加しました。
輸送と護衛に汗を流していた第八駆逐隊でしたが、2月19日、2隻の輸送船を伴ってマカッサルからバリ島へ輸送を行っていました。
揚陸中に空襲を受けて輸送船が2隻とも損傷したため、第二小隊の【満潮、荒潮】は一足先に【相模丸】を護衛してマカッサルへ、【笹子丸】は第一小隊の【朝潮、大潮】とともに夜が来るまで身を潜めました。
しかし20日を迎えようとしていた時、闇夜に紛れてバリ島から撤退しようとした3隻に対してABDA艦隊がその行く手を遮ります。
「バリ島沖海戦」の勃発です。
ところがこのABDA連合艦隊、しっかりとした統率や指揮系統が確立されておらず、同海域で日本に攻められては困る国々が寄せ集まったような状態でした。
まず先頭にいた【蘭軽巡洋艦 デ・ロイテル】と【蘭ジャワ級軽巡洋艦 ジャワ】が砲撃を仕掛けてきますが、数的に不利ではあるものの2隻の軽巡は本格的な砲戦を避け、すぐに引き揚げてしまいます。
軽巡を失った第二小隊は追撃を始めますが、発見したのは軽巡ではなく【蘭アドミラーレン級駆逐艦 ピート・ハイン】でした。
この時【ピート・ハイン】は突出しており、【朝潮】は遭遇した【ピート・ハイン】に向けて砲撃、雷撃を行います。
【ピート・ハイン】は大した反撃もできずに大破炎上し、やがて沈没。
【朝潮】は【大潮】と共に撤退する2隻の駆逐艦を発見していますが、深追いはせずに周辺の警戒に戻りました。
午前3時ごろを過ぎると第一小隊は再び敵を発見。
海戦はこの後も第二次~第四次と続きますが、途中で援護に加わった第二小隊が結果的に挟み撃ちにあってしまい、【満潮】が大破してしまいました。
海戦としてはさらに【トロンプ】と【米クレムソン級駆逐艦 スチュアート】の撃破に成功して勝利を収めていますが、海戦後も空襲を受けて【満潮】に至近弾、【大潮】も同じく至近弾を受けて浸水が発生してしまいます。
この結果、第八駆逐隊は一時的に半壊、【朝潮、荒潮】の2隻だけになりました。
【朝潮、荒潮】はその後もジャワ島攻略に参加し、ひと段落ついてから本土に帰還。
2隻とも3月25日から4月15日まで横須賀で整備修理を行いました。
修理を終えた直後、横須賀にもその爆音が届いたでしょうか、まさかのアメリカによる東京空襲が行われました。
「ドーリットル空襲」です。
急いで本土に残る艦艇に命令して機動部隊の捜索が始められましたが、すでに【米ヨークタウン級航空母艦 ホーネット、エンタープライズ】は逃走していたために発見できませんでした。
どころか日本に戻る最中に巻き込まれた悪天候で、【荒潮】が一番主砲の防水帯が故障(剥がれ?)による浸水、【朝潮】は負傷者発生と散々なものでした。
散々なのはこれだけではありません。
第七戦隊の護衛として参加した6月5日からの「ミッドウェー海戦」では、第七戦隊の問題行動に付き合わされた挙句、衝突損傷した【最上】【三隈】の護衛をさせられます。
その2隻は空襲によってさらに痛めつけられ、もちろん【朝潮、荒潮】も巻き込まれてしまいました。
最終的に【三隈】は沈没し、【朝潮、荒潮】はできるだけ救助を行いますが、【朝潮】も被弾して燃料タンクを損傷、【荒潮】も至近弾で人力操舵に切り替えざるを得なくなります。
何とか逃げ切った3隻でしたが、この歴史的敗北は日本の行く末そのままでした。
【朝潮】は修理後に船団護衛や哨戒活動を行いますが、10月末にラバウルへ進出。
早速鼠輸送という背に腹は代えられない任務を背負い、最前線の戦いの苦境を思い知らされます。
11月13日には、前日の「第三次ソロモン海戦第一夜」による【比叡】ら沈没を受けてもなお輸送を強行しなければならないジリ貧の状態の中、ショートランド泊地に残る第七戦隊がヘンダーソン飛行場への艦砲射撃を行うことになりました。
しかしそこを狙ったショートランド泊地への空襲で、同行する予定だった【満潮】が大破します。
この影響で第八艦隊と行動を共にするはずだった【朝潮】が第七戦隊の護衛に変更。
砲撃自体は無事に行えましたが、効果は薄く、逆に蜂の巣をつつく行為であったことを思い知らされます。
引き揚げる第七戦隊と、途中で合流している第八艦隊は、その後方からバタバタといううるさい音に血の気が引きます。
今しがた砲弾をありったけぶち込んだヘンダーソン飛行場から、またしても航空機が飛んできたのです。
何回撃ってもすぐ反撃されるおなじみのパターンに嫌気がさしますが、四の五の言ってられません、すぐさま対空射撃が始まりました。
しかし飛行場と【エンタープライズ】からの艦載機による空襲は的確で、【衣笠】撃沈、【五十鈴】大破、また艦砲射撃を隠れ蓑にして別ルートで進んでいた輸送船団もばっちり狙われてしまい、船団も11隻中6隻を失うという大惨事となりました。
その後「ブナ・ゴナの戦い」の支援の輸送が始まりますが、ここでも船団を狙う空襲が後を絶ちません。
11月18日には一緒に輸送を行っていた【海風】が【B-17】の爆撃を受けて大破してしまい、【朝潮】がラバウルまで曳航しています。
その【朝潮】も12月8日の空襲で至近弾を受けてしまい後部砲塔2基を損傷しましたが、その後も応急修理程度で済まされてすぐにカビエンやラバウルへの輸送を強いられました。
そして12月22日、ショートランド泊地で爆撃を受けてからほとんどほったらかし状態だった【満潮】がようやく修理を受けれるようになりました。
【朝潮】がトラックまで【満潮】を曳航し(【天霧】護衛)、そこで【満潮】は【明石】による修理が行われます。
一方【朝潮】もこの避退によって「ガダルカナル島の戦い」から離脱。
昭和18年/1943年1月7日には【瑞鶴】や【陸奥】らと共にトラックを発ち、横須賀へと戻っていきました。
2月20日、【大潮】が【米ガトー級潜水艦 アルバコア】の雷撃を受けて大破、のち沈没しました。
【大潮】が被雷したのはビスマルク海に浮かぶマヌス島の北で、ビスマルク海はラエやニューギニアを目指す上で必ず通過しなければならないエリアでした。
ビスマルク海の東側はラバウルがありますが、南側のニューブリテン島とパプアニューギニアに挟まれたビスマルク海からダンピール海峡というのは、「ブナ・ゴナの戦い」が終結した後はニューギニア島南端を連合軍が掌握したため、海峡沿いにあるラエへの日本の支援を遮るためにも重要な場所でした。
当然日本側も「ポートモレスビー作戦」の失敗によってラエやサラモアの防備増強は急務でした。
1月7日から8日にかけて、ラバウルからウェワクへの輸送が成功。
これに続いてガダルカナル島から撤退した兵士たちを含めた陸軍兵をニューギニア島の各署へ派遣することが決まりました。
これを「八十一号作戦」と呼びます。
「八十一号作戦」はラエ・サラモア、マダン、ウェワクの3ヶ所に陸軍を輸送する作戦でした。
この中でぶっちぎりに危険なのがラエルートです。
ラエはポートモレスビーから最も近く、また唯一ダンピール海峡を通過しなければなりません。
そして連合軍も圧倒的に攻めやすい位置なので、底なし沼の看板があるのに沼に入っていくようなものでした。
もちろん反対意見が噴出しますが、第八艦隊作戦参謀の神重徳大佐を始め幹部たちは意見を曲げません。
第三水雷戦隊参謀であった半田仁貴知少佐は、実際に神大佐に対して作戦中止を求めていますが、「命令であるから全滅覚悟でやってもらいたい」と取り付く島もありませんでした。
ラエの補強は絶対であり、マダンからの陸路ではずいぶん時間がかかるため仕方ない一面もありますが、手厚い支援もないのに突っ込めとは無慈悲極まりないでしょう。
ともあれ命令なのでやるしかありません。
ラエへの輸送は【朝潮、荒潮】を始め8隻の駆逐艦、そして7隻の陸軍輸送船と【給炭艦 野島】が行うことになりました。
2月28日出撃、突入は3月3日となりました。
【野島】は大正時代に建造された、駆逐艦で言うと「神風型」時代の給炭艦です。
最高速度はわずか12ノットでしたが、別にこれは輸送船としては珍しい速度ではありません。
【野島】艦長の松本亀太郎大佐は、第八駆逐隊司令の佐藤康夫大佐の1つ後輩で同じ分隊だった時期がありました。
出撃の前日、2人は残り数日となった命を肴に酒を飲み交わしていました。
松本大佐は「脚の遅い野島は必ず犠牲になります。骨は拾ってください」と伝えます。
これに対し佐藤大佐は「私の朝潮が護衛する限り、決して見殺しにはせん。野島の乗員は必ず拾いにゆく」「やられたらお互い必ず救ける」と固く約束しました。
2月28日深夜、旗艦【白雪】が率いる船団がラエへ向けて出撃しました。
そしてそれは、どれだけ覚悟を積もうがなお足らぬ冥土への入り口でした。
3月2日、船団に敵機が迫ってきました。
前日にはすでに触接を受けていて、無事に済むわけがないことは皆がわかっていました。
2日の空襲では【旭盛丸】が沈没。
ラバウルからの直掩機が援護に出ていたものの、敵機より多いわけでもないし相手も護衛の戦闘機を引き連れていますから爆撃を妨害するのはなかなか難しいのが現実でした。
そしてあくる3日、ダンピール海峡に差し掛かったところで怒涛の爆撃が船団を食い散らかしていきました。
やはり敵機の数が多い中直掩機の爆撃阻止は不可能に近く、足止めを食らった【零式艦上戦闘機】を尻目に次々と爆弾が空から、否、横から突っ込んできたのです。
アメリカが編み出した反跳爆撃、これは水切り石の要領で魚雷のように低空から爆弾を投下し、海面を爆弾が跳ねて標的に命中させるという攻撃方法でした。
この方法は雷撃機と同じ攻撃の仕方になりますから、艦隊に対してほぼ水平に落下してきます。
艦船からの機銃攻撃が命中しやすいため危険なのですが、日本の艦船は機銃が少ないことは知っていましたし、そして事前の機銃掃射で甲板上の兵士を攻撃し、機銃を扱える人数そのものを減らしてから攻撃することでその危険性を軽減させたのです。
さらに水平爆撃と組み合わせることで、船団は上と横の二方面からの攻撃に振り回されることになります。
最初の空襲で【白雪】【荒潮】【時津風】が被弾し、そして3隻はいずれも最終的には沈没しています。
辛くも無傷でこの難局を乗り切った【朝潮】ですが、【野島】からは火の手が上がっており、沈没は時間の問題でした。
【白雪】から司令を引き継いだ【敷波】は第二波の空襲が迫っているという報告を受け、救助活動を中断し、残りの船と共に避難することを命令します。
しかし【朝潮】は「ワレ野島艦長トノ約束アリ、野島救援ノ後避退ス」とこの命令を振り切り、【野島】と同じく炎上中の【荒潮】(被弾後操舵不能で【野島】に衝突)の救助に向かいました。
負傷兵や陸軍兵が優先的に【朝潮】に移乗。
続いて【野島】の乗員と松本大佐を救出した【朝潮】でしたが、逃げ切れる時間はもう残されていませんでした。
報告のあった敵機が命あるものすべて滅ぼすつもりで再び爆撃が始まりました。
特に避難するためにちょこまか動くうるさい【朝潮】は目ざわりで、最初に集中的に爆弾が投下されました。
四方八方から襲い掛かる爆弾になす術もなく、【朝潮】は大破、そして沈没していきました。
松本大佐は佐藤大佐によって【野島】から脱出できました。
【朝潮】沈没後も漂流しているところを夜になって引き返してきた駆逐艦に救助されました。
しかし自身は【朝潮】から離れることはありませんでした。
佐藤大佐は「もう疲れたよ」と脱出を拒否、前甲板に座り込み、勇気ある駆逐艦【朝潮】とともに沈んでいきました。
【朝潮】艦長の吉井五郎中佐、一時は救助された【荒潮】の艦長久保木英雄中佐も戦死し、ここに「ビスマルク沖海戦」、通称「ダンピールの悲劇」は終結します。
この海戦では先の3隻の駆逐艦どころか、参加した輸送船全てが沈没しています。
船団だけでなく、陸上火砲41門、自動車89両、物資2,500tも海の藻屑となり、また同時に修理によって同海戦に参加していなかった【満潮】を除き、第八駆逐隊は全滅。
たった数週間で、【満潮】は自身の修理中に僚艦をすべて失ってしまいました。