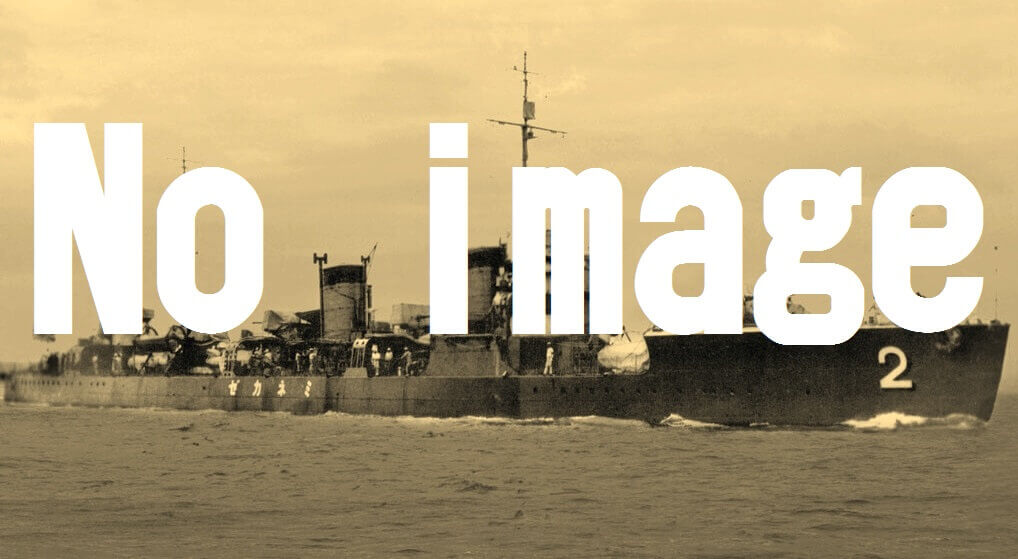| 起工日 | 昭和11年/1936年12月1日 |
| 進水日 | 昭和12年/1937年11月18日 |
| 竣工日 | 昭和14年/1939年6月28日 |
| 退役日 (沈没) | 昭和20年/1945年4月7日 |
| 坊ノ岬沖海戦 | |
| 建 造 | 浦賀船渠 |
| 基準排水量 | 1,961t |
| 垂線間長 | 111.00m |
| 全 幅 | 10.35m |
| 最大速度 | 35.0ノット |
| 航続距離 | 18ノット:3,800海里 |
| 馬 力 | 50,000馬力 |
| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 3基6門 |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |
| 次発装填装置 | |
| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |
| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 3基 |
| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |
忌まわしき7.5 北に嫌われた霞
【霞】は【霰】【陽炎】【不知火】とともに第十八駆逐隊を編成し、第二水雷戦隊に所属。
艦型が「朝潮型」と「陽炎型」が混ざっていますが、両者の設計に他の艦型ほどの違いがないので、運用上の障害にはなりませんでした。
太平洋戦争の開幕戦となった「真珠湾攻撃」では、補給部隊を護衛して出撃。
ただしばらくは二水戦から一時抜けて第一航空艦隊に所属して4月まで働きます。
ド派手な戦果を残して日本に凱旋しました。
ただこの時【霞】と【霰】の航続距離は「陽炎型」に比べて短いことから、艦内には予備として18ℓの燃料入りのドラム缶がたくさん搭載されていました。
帰投後も機動部隊の護衛として各作戦に参加。
重要な作戦としては日本の一大拠点となったラバウルの攻略です。
「R作戦(ビスマルク作戦)」と呼ばれるこの作戦では、ラバウルやビスマルク諸島、カビエンの攻略を昭和17年/1942年2月上旬には完全に達成しました。
一方で2月1日に日本はアメリカの反撃である「マーシャル・ギルバート諸島機動空襲」の被害を受けます。
この追撃に【赤城】らが出動していますが、他の部隊含めてこの空襲は撃ち逃げされてしまい捉えることができませんでした。
ですが日本の勢いはとどまるところを知らず、ポートダーウィンの空襲、チラチャップへの空襲、そして4月には「セイロン沖海戦」でイギリス軍の基地があったセイロン島を徹底的に破壊。
これでイギリスの東洋艦隊は前線を下げざるを得ず、以後の日本の目下の敵はアメリカとオーストラリア、ニュージーランドとなったのです。
常に花形だった機動部隊を護衛してきた【霞】ですが、「セイロン沖海戦」を終えたあとに本土に帰投し整備を行います。
次の壮大な作戦が、日本の未来をより明るくする、そう誰もが思ったことでしょう。
ところがその壮大な作戦は、その夢を牽引する4隻の空母をむざむざ沈めるという、目を覚ますにしても限度があるだろというほどの取り返しのつかない結果を残して大失敗します。
言うまでもなく「ミッドウェー海戦」です。
【霞】はこの海戦では空母ではなくミッドウェー島攻略部隊の護衛として参加していますから、つい数ヶ月前まで行動を共にしてきた勇壮な空母たちの最期を見届けることはできませんでした。
【霞】の不幸はこれに留まりません、むしろ自身の不幸はこちらのほうが圧倒的です。
「MI作戦」は崩壊しましたが、アリューシャン列島攻略の「AL作戦」は一部だけ達成されています。
第十八駆逐隊は第五艦隊に所属し、この北方海域での活動を命じられて船団護衛や哨戒活動を行うことになりました。
そんな中、【霞、霰、不知火】は6月28日に【千代田】【あるぜんちな丸】を護衛して横須賀を出港し、キスカ島まで輸送を開始。
【陽炎】は【山風】が行方不明(当時)になったことで東京での対潜哨戒任務を代わりに行うことになったため不参加です。
道中は至って平穏でしたが、7月4日、アリューシャン列島が近づくと視界を遮る濃霧が5隻を包み込みました。
この海域では、特に春から夏にかけて気温差による濃霧がしょっちゅう発生し、また夜間ということでこのまま無理をすると座礁の危険もありました。
またここ数週間は連日働き通しだったこともあり、なので駆逐艦3隻は無理に入港をせず、第十八駆逐隊司令の宮坂義登大佐は、休息も兼ねて揚陸は日が昇ってからにすると命じます。
輸送の2隻は湾外に留まらずに入港し、揚陸を行っています。
霧も深かったので敵襲の恐れもないだろうという考えもあったかもしれませんが、夜が明けきる前に霧は濃淡を繰り返しながらも徐々に晴れていきました。
そして視界が良好になったことで、潜水艦から見れば格好の的になってしまったのです。
霧が晴れたら報告するようにと念を押していたのですが、敵はこの隙を逃しませんでした。
3隻に狙いを定めていたのは、【米ガトー級潜水艦 グロウラー】でした。
午前3時ごろ、【グロウラー】は3隻それぞれに1本ないし2本の魚雷を放ち、そして次の瞬間、ドカーン、ドカーンと耳をつんざく音と同時に足場が大きく揺らぎました。
3隻それぞれに魚雷が1本ずつ命中し、うち【霰】は船体断裂の憂き目にあい、あえなく沈没。
この時【霰】は沈没する前に【グロウラー】を視認して砲撃を行いましたが、恐らく追撃の1本がさらに命中したことで【霰】の息の根を止めました。
【不知火】は魚雷を機関部付近に受けたほか艦尾の甲板も屈曲したことで全く動くことができず、【霞】もまた艦首への被雷により火災と右屈曲で航行不能に陥ります。
一瞬にして1隻沈没2隻大破という大惨劇となってしまったキスカ沖。
【グロウラー】がそのあと立ち去ってくれたおかげで【霞】と【不知火】は何とか生き長らえましたが、それでも2隻は身動きが取れません。
すぐそばで【霰】が沈んでしまっているのに、助けることもできないのはどれほどもどかしかったことか。
懸命な応急修理の末、【不知火】は前進、【霞】は後進でキスカ湾にまで入港することができました。
その後はキスカ島で空襲を受けて沈没していた【日産丸】の陰に隠れて修理を行い、また修理用の物資も【陽炎】や【長波】が横須賀から運んできてくれました。
【霞】は26日に曳航が可能なまでに回復したことで、27日には【雷】の曳航、【陽炎】の護衛を受けてキスカ島を出港。
その後幌筵で【電】に、さらに石狩で【富士山丸】に曳船がバトンタッチされ、8月13日に舞鶴に無事に到着し、ようやく本格的な修理が始まりました。
第十八駆逐隊はこれで活動できるのが【陽炎】だけになってしまったので、15日に解隊。
【陽炎】は第十五駆逐隊に異動となりました。
【霞】はここから修理に10ヶ月を擁し、被害を受けてから約1年でようやく本来の形に戻ることができました。
この修理中に九三式水中探信儀を増設されています。
修理を終えた後は第十一水雷戦隊で訓練や試験協力を行い、昭和18年/1943年9月1日に第九駆逐隊に編入されます。
そして【霞】は早くも憎き思い出のある北方海域へと向かうのです。
しかし今回は何事もなく任務を遂行することができました。
ところが北は大きな動きがなくても南は時々刻々と情勢が変わっています。
戦力補充のために臨時で内南洋部隊の指揮下に入り、横須賀経由でルオットへの緊急輸送を実施。
その後はトラックに向かい、ラバウルで空襲を受けていた【最上】を護衛して呉へ向かいました。
【最上】を送り届けた【霞】は、そのまま北に戻るのではなく自身も舞鶴へ向かいます。
そしてここで対空兵装強化の為に2番砲塔が撤去され、代わりに25mm三連装機銃が2基設置されました。
電探も22号対水上電探と13号対空電探がそれぞれ1基、恐らくこのタイミングで装備されていると思います。
その後北へと戻った【霞】ですが、昭和19年/1944年3月15日、ここまで難を逃れてきた第九駆逐隊もついに被害を受けてしまいます。
【薄雲】【白雲】とともに4隻の輸送船を護衛して、小樽から釧路経由で得撫を目指していました。
当然潜水艦を警戒しながらの航行となりますが、この中で慎重になりすぎたのか、輸送船の【日蓮丸】が暗闇の中でチラッと目に入った艦影に突如砲撃を行います。
その砲撃を受けたのが【白雲】だったのですが、【白雲】はこの中で発光信号を放って誤射を止めさせようとしました。
恐らくこのやり取りが、【米タンバー級潜水艦 トートグ】の知るところとなったのでしょう、【白雲】はこの後この【トートグ】の魚雷を受けて轟沈してしまったのです。
その後【トートグ】は【日蓮丸】も沈めており、【霞】は爆雷を投下しますが【トートグ】は被害なく撤退に成功。
船団は【薄雲】が護衛して釧路まで引き揚げ、また対潜哨戒はその後応援を受けて広範囲で行ったもの、手応えはありませんでした。
【白雲】の喪失によって第九駆逐隊は解隊。
実は3月1日に【不知火】が第九駆逐隊に編入されていたのですが、この時彼女は南にいたため同行しておらず、解散後は【霞、薄雲、不知火】の3隻で、面子こそ違いますが再び第十八駆逐隊を編成するに至りました。
ただ第十八駆逐隊は「マリアナ沖海戦」とそれに関する作戦には参加しておらず、しばらくは第五艦隊と行動を共にしていました。
さらに7月5日には【薄雲】も船団護衛中(第十八駆逐隊とは別行動)に沈没しており、第十八駆逐隊も2隻となってしまいます。
| 昭和19年/1944年9月2日時点の兵装 |
| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 2基4門 |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |
| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |
| 25mm連装機銃 1基2挺 | |
| 25mm単装機銃 8基8挺 | |
| 13mm単装機銃 4基4挺 | |
| 電 探 | 22号対水上電探 1基 |
| 13号対空電探 1基 |
出典:日本駆逐艦物語 著:福井静夫 株式会社光人社 1993年