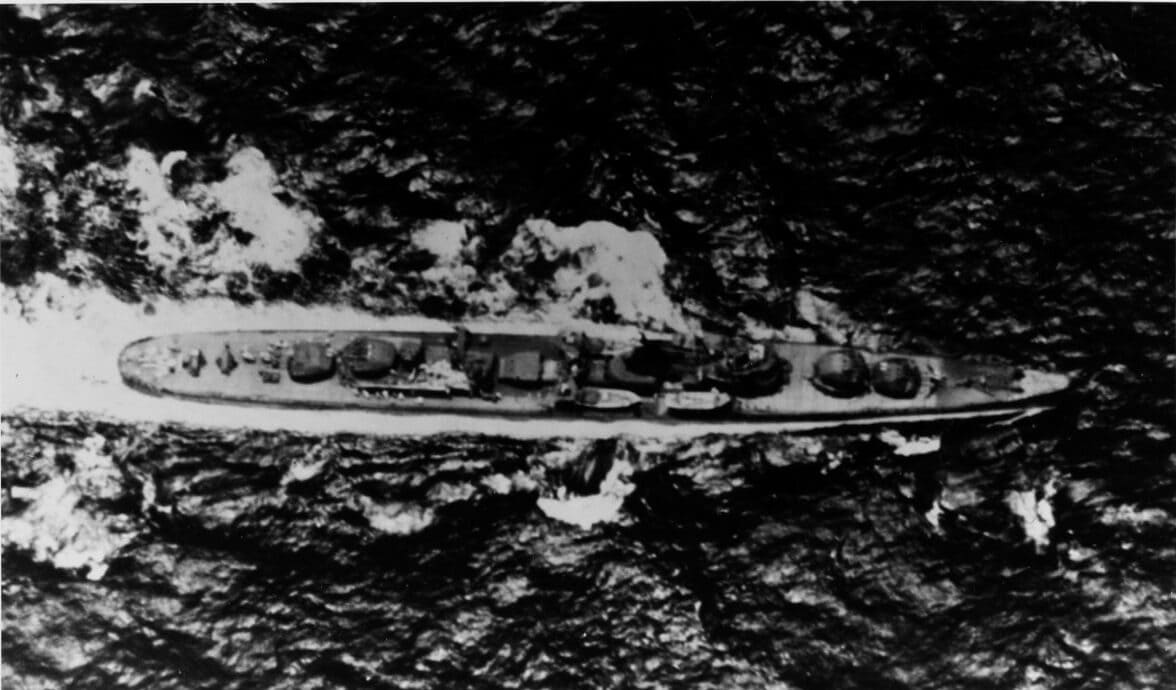| 基準排水量 | 2,700t[2-P72] |
| 満載排水量 | 3,887t[2-P72] |
| 公試排水量 | 3,470t[2-P72] |
| 垂線間長 | 126.00m |
| 全 幅 | 11.60m |
| 最大速度 | 33.0ノット |
| 航続距離 | 18ノット:8,000海里 |
| 馬 力 | 52,000馬力 |
| 主 砲 | 65口径10cm連装高角砲 4基8門 |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 次発装填装置 |
| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |
| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 3基 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |
日本の防空艦構想と秋月型の誕生
太平洋戦争の主役となり、そして現代においてもなお有人兵器としては主役である航空機。
陸上ではもちろん陸上基地から、海上では航空母艦を住処として圧倒的な広範囲を掌握し、そしてひとたび襲い掛かれば四方八方から致命的なダメージを負わす攻撃を理不尽に繰り出す航空機は、太平洋戦争の大局を左右する存在でした。
特に海軍においては、第一次世界大戦では存在しなかった海上での航空戦を実現する空母の誕生が革命的でした。
空母に関しては米英が既存艦の改装、日本は新造艦から歴史がスタートしています(厳密には日本は水上機母艦の【若宮】が日本初の空母となっていますが、これは逆に水上機母艦という分類がなかったために空母となっています)。
その後各国空母の研究と建造には殊更力を入れ、そして同時に艦載機の開発速度も劇的に速くなっていきいました。
また空母の発展に伴い、水上艦は敵空母からの攻撃に対処するために徐々に高角砲や対空機銃を装備するようになっていきました。
1920年代前半からたった15年足らずで空母の性能や戦局への影響力は爆発的に拡大。
日本は「翔鶴型」2隻の竣工が開戦時期に大きく影響していますし、アメリカも空母建造と合わせて1930年代中盤から水上艦の対空兵装強化を行っています。
日本も同時期にはまだ対空兵装は貧弱ではあったものの、会議の中では空母建造の加速と並行して機銃の大幅増備をすべきという意見も多数出ていました。
それだけ空母の力は侮れないものとなっていたのです。
そんな中、にわかに話題となってきたのが、「防空艦」という概念です。
その名の通り防空に特化した艦のことで、これまでのように対水上艦との戦闘を想定した装備ではなく、艦載機からの攻撃を撃退するための艦の配備が必要だというのです。
日本で対空兵装が豊富なのは強いて言っても空母のみ、戦艦もそれなりに機銃は備えていますが、巡洋艦と駆逐艦は些細なものしかありません。
このままでは空母の攻撃力は高まっても空襲に対する防御力は貧弱さを増す一方。
この状況に危機感を感じた日本は、防空に特化した艦を配備して艦隊・戦隊・空母などを直衛する艦の建造を計画したのです。
日本はここにきてようやく防空に力を注いだかのように見えますが、成果としては失敗の部類となりますが以前から防空の意識はありました。
それが主砲の高角砲化です。
例えば駆逐艦の12.7cm砲B型が仰角75度、20cm連装砲E型は仰角70度まで対応できるようになっており、また同時に方位盤高射式装置を備えたことで対航空機用の装備は整えられていたのです。
速射性の問題があって使い勝手は良くありませんでしたが、防空軽視一辺倒ではなかったことは忘れてはなりません。
しかしこれはあくまで個艦防空であって、防空艦とはコンセプトが異なります。
防空艦議論を後押ししたのが、イギリスが旧式の「C級軽巡洋艦」の兵装を防空特化に改める改装を行ったことです。
これは45口径15.2cm単装砲5基の主砲と39口径7.6cm単装砲2基を全部撤去して、10.2cm単装高角砲10基へ換装し、また4cm単装ポンポン砲2基は四連装ポンポン砲へ、魚雷は撤去するというもので、完全に対空兵装のみの艦となったのです(この兵装は時期と艦によって異なります)。
さらにイギリスは新造艦としても、防空巡洋艦として類似の兵装と53.3cm三連装魚雷発射管を持つ「ダイドー級軽巡洋艦」も昭和12年/1937年から建造し始め、本格的に航空機対策に踏み切りました。
引き続いてアメリカも「アトランタ級軽巡洋艦」の設計を行います。
「アトランタ級」は「オマハ級」の置き換えだったために昭和14年/1939年以降の竣工が認められていて、これ以降の竣工を目指して38口径5インチ(12.7cm)連装両用砲8基、28mm四連装機銃4基、20mm単装機銃6基と53.3cm四連装魚雷発射管2基を搭載した軽巡洋艦です。
サイズ的には軽巡洋艦ですが、この両用砲は何と日本の駆逐艦の50口径12.7cm砲よりも短砲身という異色の砲です。
当然射程も50口径12.7cm砲よりも短いのですが、両用砲ですから仰角を上げても分間12~15発(人力装填)と十分な速さを持っています。
1番艦の【アトランタ】は昭和13年/1938年計画、昭和15年/1940年から建造が始まりました。
仮想敵国が立て続けに防空巡洋艦を建造する中、日本もさほど遅れることなく昭和12年/1937年から具体的な防空巡洋艦の検討が行われました。
元となったのは、「C級」よりも少し前に建造され、すでにかなりの旧式となっている「天龍型」でした。
正直このままでは「天龍型」は練習艦などに格下げになるのが決定的だったので、最終的には新造するにしても一度試験もかねて既存艦を改装するのは、少ない予算でやりくりする上でも当然だったかもしれません。
この時の「天龍型」の改装では、40口径12.7cm連装高角砲4基、25mm三連装機銃4基、九四式高射装置に加え、九三式爆雷投射機と九四式爆雷投射機各1基、爆雷装填台2基、手動投下台4基、また煙幕発生機を搭載しボイラーも重油専焼缶へ換装するとされています。
米英の防空巡洋艦に比べるといささか貧弱ですが、三国の中では「天龍型」が最も排水量が少ないため止むを得ません。
同時にカタパルトと航空機を搭載する計画もあったようです。
ですが改装案を進める上で、今の主砲の位置にそのまま高角砲を搭載すると射角の狭さが問題となり、射角を優先すると艦橋を造り直す必要がある、艦橋をそのままにすると防空艦としての性能が落ちるという問題がありました。
つまり改装するには大げさだし、楽に造るとイマイチ効果が上がらないという、どっちにしても費用対効果が悪いということがわかったのです。
「天龍型」の改装案は1938年~1940年度案の3回も提出されたのですが、予算が通過したのは1940年度。
そして通過しても改装後の性能が疑問視されたことで、結局「天龍型」の改装は幻となってしまいました。
これに対し、日本も「ダイドー級」や「アトランタ級」に並ぶ新造防空艦を建造する計画がありました。
いわゆる「815号型軽巡洋艦」と呼ばれるものです。
「マル5計画」で姿を見せたこの「815号型軽巡」は、排水量5,800t程度と「阿賀野型」よりも軽く、「秋月型」と同じ長10cm砲を4基8門、そして航空機2機とカタパルトを搭載するというものでした。
これ以上の情報はなく、また「マル5計画」は「改マル5計画」によってガラリと様相を変えてしまったので、「815号型軽巡」は人知れず消滅していきました。
これ以上呆気なく散ったペーパープランには、排水量9,000t、長10cm砲12基24門、九四式高射装置4基というものもありました。
「天龍型」の防空巡洋艦化改装は実現しませんでしたが、防空艦の議論はより熱を帯びていました。
1937年から「天龍型」の改装案が進んでいた一方で、完全な新造防空艦の検討もされていました。
ですが巡洋艦クラスになるとさすがに予算と量産が難しいので、駆逐艦の大型化という枠内での建造が計画されたのです。
当初は駆逐艦という分類ではなく、新たに「直衛艦」という言葉で表されました。
これは初期計画案では魚雷の搭載がなかったことから、魚雷を持たない駆逐艦っていうのはなぁということで「直衛艦」となったのです。
ただ計画の内容を見てみると、これは駆逐艦サイズじゃ無理だろうという性能です。
この頃から主砲は採用されたばかりの長10cm砲を8門搭載することは決定していて、速力:35ノット、航続距離は18ノット:10,000海里というかなりの性能に加え、不時着水した航空機の救難用デリックも設けるというものでした。
他にも空母随伴ですから波浪にも強くないといけないことから、この内容だと基準排水量3,700t以上となることが確実視され、また機関も新型を搭載するか数を増やすしかなく、当然ながら駆逐艦サイズに抑えるべく計画は練りなおされました。
1938年に提出された「マル4計画」には、「乙型駆逐艦」という表現となっています。
ここで直衛艦という言葉は消滅し、防空艦は正式に駆逐艦枠での建造が決定しました。
巡洋艦とならなかった理由は上記のサイズの問題もありますが、何よりも巡洋艦分類で建造してしまうと、巡洋艦の護衛用に駆逐艦を編成する必要があるため、もっと駆逐艦の数不足が加速してしまうのです。
防空艦のために新たに組織編成を改めるのも非常に手間ですから、駆逐艦として建造する理由はそういう側面もありました。
ただし予算が増えたわけではなく、「乙型」登場の影響で当初は「夕雲型」24隻建造の予定だったものが16隻に減少し、その分が「乙型」6隻に回されています。
予算承認のために海軍省が大蔵省に訴えられた内容を引用いたします。
「1.航空戦隊には従来艦齢超過駆逐艦を付属せしめ、対空対潜警戒並に救難等に充当し居たるも、航空母艦に随伴する為には、航続力著しく不足し、航空戦隊の行動を掣肘(筆者注 せいちゅう 干渉して人の自由な行動を妨げること)するに至る不利極めて大にして、予てより所要性能を具備する別個の艦型の必要を痛感し居たるも、諸般の状況を考慮し未だ実現を見ざりしものなり。然るに海上戦闘に於ける航空機の重要性、愈々加重したる今日、海上航空兵力の主体たる、航空母艦の全幅活用を計るの要、切なるを以て、総合戦闘力向上のため、特に本艦型を選定し、6隻を建造せんとす。
2.将来の戦場に於いては、航空母艦の如き重要兵力に対しては、常時対空対潜警戒を必要とする処、本艦型の要目を適当に選定し、以て我飛行機に対する警戒救難と共に。本要求をも充足せんとするものなり。」
この「乙型駆逐艦」ですが、原案を含めて4つの計画がありました。
しかし魚雷を積まないから直衛艦という名称になったことを逆に考えると、駆逐艦になったからには魚雷は搭載することになるのです。
これは結局限られた予算と量産性から鑑みても、防空(+対潜)一辺倒は贅沢すぎるということで搭載されます。
また「甲型」6隻を「乙型」に割り当てたということは、雷撃艦を6隻失うことになりますから、戦力構想としてもやはり「乙型」には最低限の敵艦隊との戦闘力を持っていてほしいという事情もあります。
出典:『日本駆逐艦物語』 福井静夫
上記資料では第1案を除いた(第2案と類似)図と4案すべてのサイズや兵装が記載されています。
最も機動部隊護衛に秀でているのが原案で、最も対艦戦闘との併用を意識しているのが第3案、そしていずれの案もデリックを搭載しています。
後者にいくほど排水量が増大しているのは当然として、この段階では機銃はすべて25mm連装機銃2基しかないのも注目です。
甘く見ていたというよりかは、まだ艦隊の対空戦闘を経験していない中で空襲がどれほどの脅威となるのかが推し量れなかったのでしょう。
最終的には原案と第1案を組み合わせてより計画が練られていく流れとなります。
振り返ってみれば、「乙型」の魚雷が敵に発射された機会は「クラ湾夜戦」前夜に【新月】が発射した時のみのはずです。
魚雷があったから第三水雷戦隊旗艦になったわけですが、魚雷がなければこのように水上戦で沈むこともなかったかもしれません。
さらに【秋月】は原因は別として魚雷の誘爆によって沈没していますし、とても「乙型」に必要な装備だったとは言えません。
ともあれ、基本計画番号「F51」となる「乙型」は1939年4月ごろには設計がまとまりました。
速度は33ノット、航続距離は18ノット:8,000海里となりましたが、これは艦隊護衛を重視すると速度は必ずしも「甲型」ほどは必要ない、しかし巡洋艦以上の艦に随伴するために凌波性と航続距離は同程度必要とのことで、航続距離が重視されたのです。
8,000海里は最新の「翔鶴型」には劣るものの、それ以前に建造された空母には十分対応できるものでした。
参照資料(把握しているものに限る)
Wikipedia
[1][歴史群像 太平洋戦史シリーズVol.23]秋月型駆逐艦 学習研究社
[2]軍艦開発物語2 著:福田啓二 他 光人社