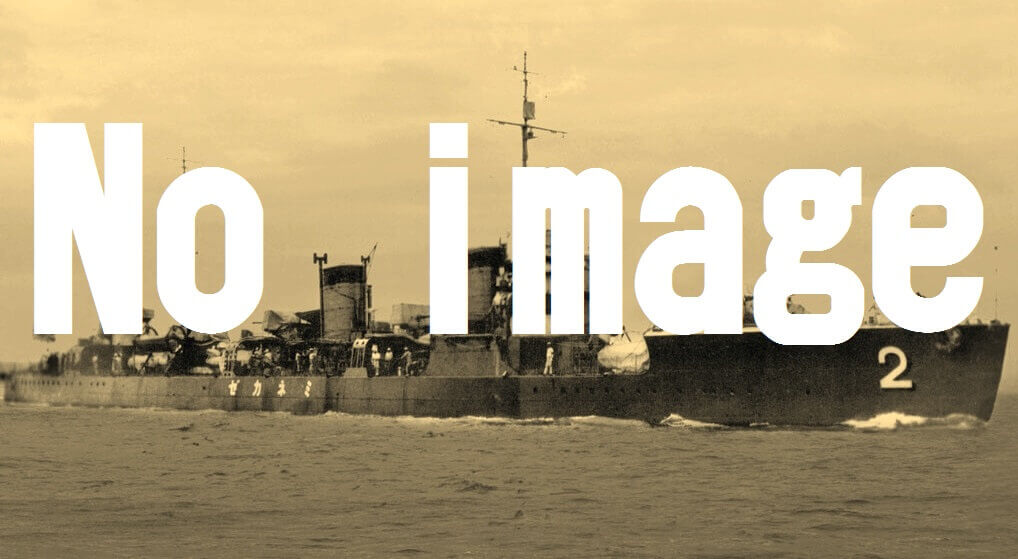| 起工日 | 昭和17年/1942年3月27日 |
| 進水日 | 昭和18年/1943年3月12日 |
| 竣工日 | 昭和18年/1943年7月27日 |
| 退役日 (沈没) | 昭和18年/1943年11月11日 |
| ラバウル空襲 | |
| 建 造 | 浦賀船渠 |
| 基準排水量 | 2,077t |
| 垂線間長 | 111.00m |
| 全 幅 | 10.80m |
| 最大速度 | 35.0ノット |
| 航続距離 | 18ノット:5,000海里 |
| 馬 力 | 52,000馬力 |
| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 3基6門 |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |
| 次発装填装置 | |
| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |
| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |
| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |
外の世界に疎いまま沈んだ涼波
【涼波】は竣工後に十一水雷戦隊(旗艦【龍田】)に所属し、8月20日には竣工が続いた【藤波】【早波】とともに第三十二駆逐隊を編成。
実は第三十二駆逐隊で最も年長者となる【玉波】はこの時には編入されておらず、【玉波】が加わるのは10月1日となっています。
9月30日には第十一水雷戦隊から第二水雷戦隊への異動が決定します。
しかし第三十二駆逐隊は引き続き第十一水雷戦隊の指揮の下におり、この後の任務も第十一水雷戦隊として参加しています。
その任務というのは、陸軍第五十二師団の甲支隊をポナペ島へ輸送する丁三号輸送というものでした。
メンバーは【山城】【伊勢】と第十一水雷戦隊で、言っちゃなんですが戦力として計算していない船でも遊ばせるのはもったいないということでの抜擢です。
丁三号輸送部隊は10月15日に出撃して20日にトラック島へ到着。
ちなみに前述のとおり10月1日に【玉波】も第三十二駆逐隊に配属となっていますが、彼女はすでに前線で仕事をしていたしたので、もちろんこの任務には参加していません。
どころか第三十二駆逐隊として【玉波】が活動する機会も、次のラバウルまでの護衛だけでした。
トラック到着後は目下の目標であるポナペへの輸送が行われます。
ポナペへは戦艦を使った輸送を行わないため、戦艦に積んだ物資はより小型の船が引き受けなければならず、輸送は3回に分けて行われました。
輸送は全て無事に終えることができ、その後【龍田】は第十一水雷戦隊として日本へ帰国。
しかしすでに二水戦であった第三十二駆逐隊の3隻は同行せず、いよいよ本格的に任務につくことになります。
11月3日、【涼波】ら二水戦はトラックを出撃。
威風堂々、筋骨隆々の重巡洋艦が揃って波を起こして進む姿に、皆気持ちが昂ぶったことでしょう。
彼女たちは「ブーゲンビル島の戦い」にて日本を追い詰めてくるアメリカ艦隊を叩き潰すために、ラバウルを目指していました。
ところが戦況は重巡達による反転攻勢を願えるほどの状況ではなく、「ブーゲンビル島の戦い」は早くも窮地に陥り、それだけでなくラバウルの制空権すら怪しまれるほどでした。
なのでラバウルへ向かう道中も安全ではなく、ラバウルよりも遥か北、ニューアイルランド島突端のカビエン沖でも空襲される状態でした。
空襲を受けたのは【涼波】達ではなく、同じくラバウルに向かっていた【島風】【天津風】とその護衛を受けていた【日章丸、日栄丸】で、【日栄丸】が航行不能となってしまいます。
この報告を受けて、ラバウル組だった【涼波】と【鳥海】が救援に向かうように命令を受けます。
また逆にトラックへ戻る予定だった【妙高】【羽黒】も同じく救援に向かっており、まず【日栄丸】を【羽黒】が曳航し、その周辺を【涼波、天津風、鳥海、妙高】で護衛してトラックへ向かうことになりました。
【島風】と【日章丸】はそのままラバウルへの輸送を継続しています。
あの重巡達がこの後どんな活躍をするかと期待を胸にしたためていたかもしれない【涼波】でしたが、ラバウルに直行しなかったのは大きな幸運でした。
5日に到着した直後、ラバウルは空前の大空襲を受けて、重巡達は見事に返り討ちにあってしまったのです。
被害の酷い【摩耶】を除き、重巡は全て何も成し遂げることなくトラックへと引き返していたました。
この空襲の報告を受けて、トラックに戻った後再びラバウルを目指していた【涼波】と【鳥海】は撤退。
その後少し時間をあけて、「ろ号作戦」のために再び二水戦にラバウルへ向けての出撃命令が下ります。
二水戦は10日にラバウルに到着し、次の命令を待っていました。
しかしアメリカのラバウル空襲は1回目の戦果が想像以上だったことから、完全に使いものにならなくするために2回目の空襲が計画されていました。
そして11日、再び機動部隊による大規模な空襲がラバウルを覆い尽くしました。
この時二水戦は偵察機からの情報でまた空襲がくることを察知して脱出を図っていたのですが、残念ながら間に合いませんでした。
スコールに紛れて北へ逃げる【涼波】達でしたが、これを見逃してくれるほど敵も甘くありません。
やがて【TBF】が二水戦に突っ込んできました。
【涼波】は攻撃態勢に入ってきた【TBF】へ向けて機銃をひたすらにぶっ放します。
その機銃で1機の撃墜に成功したのですが、【TBF】は次々に【涼波】目掛けて魚雷を投下。
3本は必死の操艦で回避しましたが、4本目の魚雷が1番魚雷発射管の直下に直撃してしまいます。
その後予備魚雷格納庫からも火災が発生。
魚雷格納庫からの火災なんて誘爆待ったなしです。
さらには急降下爆撃で1発直撃弾を受けて、【涼波】の姿はボロボロでした。
やがて恐れていた通り、予備魚雷が誘爆して【涼波】の身体は断裂。
せっかく運よく5日のラバウル空襲を回避できたのに、二度目の空襲で【涼波】はたった3ヶ月半ほどの艦生を終えてしまいます。