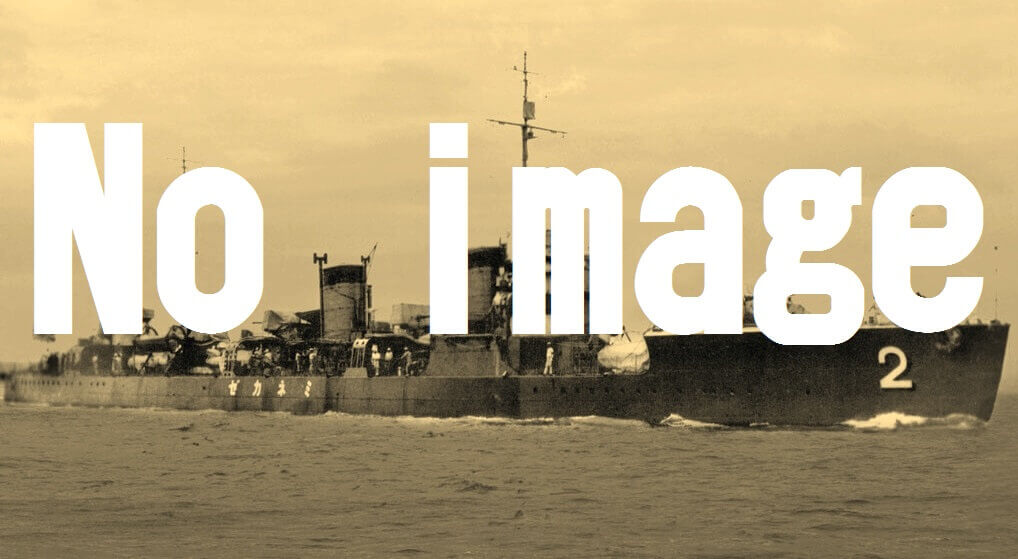| 起工日 | 昭和14年/1939年2月20日 |
| 進水日 | 昭和14年/1939年11月10日 |
| 竣工日 | 昭和15年/1940年12月15日 |
| 退役日 (沈没) | 昭和18年/1943年3月4日 |
| ビスマルク海海戦 | |
| 建 造 | 浦賀船渠 |
| 基準排水量 | 2,033t |
| 垂線間長 | 111.00m |
| 全 幅 | 10.80m |
| 最大速度 | 35.0ノット |
| 航続距離 | 18ノット:5,000海里 |
| 馬 力 | 52,000馬力 |
| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 3基6門 |
| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |
| 次発装填装置 | |
| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |
| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |
| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |
空母護衛に苦い思い出 介錯を嫌った時津風
【時津風】は【初風】【雪風】【天津風】とともに第十六駆逐隊を編成し、第二水雷戦隊に所属します。
太平洋戦争開戦後はフィリピン攻略に従事し、その後の蘭印作戦を含めてレガスピー、ダバオ、メナド、ケンダリー攻略に次々参加。
どんどん南下していく日本陸軍の護送を中心に日本の快進撃を支えました。
昭和17年/1942年2月27日にはジャワ島への上陸を前にして勃発した「スラバヤ沖海戦」に巻き込まれます。
二水戦は主力の重巡部隊の砲撃が効果がないとみるや雷撃戦を仕掛けるために敵艦隊に接近。
距離およそ9,000mというところまで迫って魚雷を次々に発射いたしました。
ところがこれらも命中することはなく、その後さらに肉薄した四水戦が砲撃によって【英E級駆逐艦 エレクトラ】を撃沈させたために二水戦は大きな活躍ができませんでした。
「スラバヤ沖海戦」は3月1日にも後半戦が行われていますが、二水戦はその後上陸の船団護衛に戻ったためにこちらには参加していません。
ただ上陸地点のクラガン周辺での対潜哨戒中に潜水艦に対して爆雷を透過しており、特に3月3日に自沈処分された【米ポーパス級潜水艦 パーチ】に対しては【天津風】や【潮】などと共同で攻撃をしています。
続いて【時津風】は同じ第一小隊の【雪風】とともに「西部ニューギニア戡定作戦(N作戦)」の一員となり、文字通りニューギニア島西部の都市や小島の制圧作戦に参加。
3月31日から掃討が始まりましたが、オランダ領だった西部ニューギニアは肝心のオランダ軍が壊滅していたので、これらはいずれも楽々手中に収めることができました。
このように連戦連勝だった日本ではありますが、6月5日の「ミッドウェー海戦」でいきなり崖から突き落とされます。
【時津風】含め二水戦はミッドウェー島攻略のための上陸部隊を乗せた船団を護衛していたため、当然海戦で敗北したとなるとその役目もなく、皆と一緒に引き返しています。
そして7月には第十戦隊へと移籍することになりました。
第十戦隊は空母護衛が主任務とされる部隊です。
その後ラバウルやトラックを回り、「ミッドウェー海戦」で手酷くやられたもののの一命をとりとめた【最上】を護衛して第十六駆逐隊は8月5日にトラック島を出発しました。
ところが僅か2日後に「ガダルカナル島の戦い」が始まり、第十六駆逐隊は【雪風】を除いて再びラバウルを、そしてガダルカナル島を目指します。
早速【時津風】は「第二次ソロモン海戦」に参戦。
8月25日、事実上の囮となった【龍驤】を護衛していた【時津風】ですが、この囮作戦は成功して【米レキシントン級航空母艦 サラトガ】【米ヨークタウン級航空母艦 エンタープライズ】の艦載機を誘引します。
【龍驤】は空母1隻での行動だったため、被弾して母艦に着艦できなくなると、艦載機も行き場を失います。
右舷45度も傾斜していた【龍驤】に着艦するのは不可能で、やがて次々と胴体着水をしていく機が現れました。
【時津風】は同じく護衛の【天津風】とこれらの救助に奔走し、またそれが終わると【龍驤】の乗員の救助にもあたりました。
【龍驤】は遂にそのまま沈没します。
この戦いで【龍驤】を護衛している【時津風】と【天津風】の姿が写真で残されています。
【龍驤】が敵の攻撃を一身に受けていたにもにもかかわらず、本丸の【翔鶴】【瑞鶴】の攻撃では、敵空母にダメージは与えましたが仕留めることができませんでした。
またその裏で行われていた輸送も【睦月】と【金龍丸】の沈没や【神通】【千歳】の中破など散々で、いよいよガダルカナル島奪還が難しくなってきました。
この結果、各島への輸送はもっぱら駆逐艦に物資を積み込んで闇に紛れて運び込むという鼠輸送が行われるようになりました。
しかし【時津風】は第十戦隊という所属の関係上、あまりこの輸送任務には参加しておらず、主に護衛任務を行っています。
10月4日、前月28日に【米タンバー級潜水艦 トラウト】の雷撃を受けていた【大鷹】を【漣】と護衛して日本へ向けてトラックを発ちます。
【大鷹】を無事に呉まで送り届けると、【時津風】はすぐさまとんぼ返り、今度は前回とは違って機動部隊の本体である【翔鶴、瑞鶴】を護衛して第三艦隊の一員として出陣し、10月26日の「南太平洋海戦」に臨みました。
この戦いでは激しい航空戦の末に【米ヨークタウン級航空母艦 ホーネット】を撃沈させましたが、一方で【翔鶴】も満身創痍で戦場から離脱。
護衛をしていた【時津風】からも【翔鶴】の惨状はよく見えたことでしょう。
勝敗は見どころによって分かれる「南太平洋海戦」ですが、基本的には日本の戦略的敗北であり、【時津風】は11月4日に【初風】とともに【瑞鶴】【妙高】を護衛してトラックを出発、日本に戻りました。
12月に入り、【時津風】は【卯月】と共に【九九式双発軽爆撃機】や物資を積んだ【龍鳳】【冲鷹】を護衛してトラックに向かう予定がありました。
ところが【冲鷹】で機関トラブルが発生したため、予定の11日に出港できたのは【時津風】と【龍鳳】だけ。
【冲鷹、卯月】はあとから追いかけることになります。
しかし何が幸運に、何が不運に繋がるかはわかりません、12日に【龍鳳】は【米ガトー級潜水艦 ドラム】の魚雷を受けて中破してしまい、撤退を余儀なくされます。
このため出発が遅れた【冲鷹、卯月】だけが無事にトラックに到着することができて、【龍鳳】はドック入り、【龍鳳】が運ぶはずだった物資などは【瑞鶴】に移載されることになりました。
31日に【瑞鶴】は【時津風、初風】と【秋月】の護衛でトラックに向かいました。
その後再び地獄の鉄底海峡に戻ってきた【時津風】でしたが、日本ももうこれ以上戦ってられんということですでに撤退に向けた準備を着々と進めていました。
ただし現地の兵士たちを救おうにも膨大な人数がいる一方で、毎日たくさんの餓死者や病死者が出る有様だったので、間もなく撤退するのに輸送は続けなければなりませんでした。
昭和18年/1943年1月10日、【時津風】は警戒隊としてガダルカナル島への鼠輸送に参加します。
しかし日本の輸送に対して様々な手段で対抗してきた連合軍は、今回もエスペランス岬沖には魚雷艇を配置。
ここで警戒隊との衝突が起こりますが、この中で放たれた魚雷が【初風】に命中してしまいます。
機関など移動するために重要な設備への被害はなかったので、【初風】は撤退することができ、【時津風】は【嵐】とともに【初風】を護衛してショートランドに戻りました。
その後も2度の輸送を行い、そして本命である大脱出作戦が2月から3回にわたって行われます。
当初は【時津風】は参加メンバーではありませんでしたが、最前線で激戦を繰り広げていた艦の整備が必要となり、ここで【涼風】【陽炎】【親潮】【長波】がトラック島に引き揚げたことで、【瑞鶴】護送の3隻がこれに代わったのです。
【時津風】はこの3回すべてに参加し、いずれもガダルカナル島の北西の先端であるカミンボへ向かうものでした。
この作戦は想定を大きく上回る成果を上げて、たとえ敗走とはいえまだまだ戦えるという気概を多少なりとも回復させた作戦だったと思われます。
とは言え戦争全体でも大きな転換点であったことに違いはなく、日本はニューギニア島の戦力増強を図ります。
ラバウルのあるニューブリテン島のすぐ西にある大きなニューギニア、ここを失うとラバウルどころかフィリピン奪還の起点になり、しかも現在進行形で一進一退、いや明らかに劣勢になってきたため、何としても盛り返す必要がありました。
そこで日本軍はラバウルからニューギニアの各地点に輸送を行う「八十一号作戦」を策定。
机上の空論で数千の命が散った「ビスマルク海海戦」の原因となる輸送作戦です。
輸送する場所はラエ、マダン、ウェワクの3ヶ所となりましたが、うちニューブリテン島との間にあるダンピール海峡を通過するのはラエのみ。
このラエ行きの輸送は絶対に危険だと反対意見が噴出しましたが、一方でとにかく叩き潰したいポートモレスビーに最も近いこと、単純に陸軍がラエまで後退していることなどが理由で、反対意見が取り入れられることはありませんでした。
しかしかたや35ノット程度の速度である駆逐艦と、出せても13ノット、標準が10ノットそこそこの輸送船では守る側も大変です。
それをポートモレスビーから近い海峡でやるのです、誰が聞いても納得できるものではありませんでした。
乗員を代表して、第三水雷戦隊参謀であった半田仁貴知少佐が第八戦隊参謀神重徳大佐へ同作戦の中止を求めましたが、「玉砕覚悟で実施してくれ」の一点張りで追い返されてしまいます。
当時から半分は被害を受けると想定され、しかも航空支援もないわけではありませんが手厚いわけでもなく、そして言うまでもなく艦艇の対空装備は弱々しい限りです。
無理無茶無謀、無慈悲。
そんな思いを乗せた、駆逐艦輸送船それぞれ8隻で構成された船団が、2月28日にラバウルを出港しました。
【時津風】はこの時第十六駆逐隊の司令であると同時に陸軍の第十八軍司令を乗せており、それだけでもかなり重要な船でした。
16隻の船団は天候がよくなかったこともあって10ノットに満たない速度で航行。
「ガダルカナル島の戦い」で危険だからと避けられた輸送船による輸送を、ここにきてまた堂々とやってしまうこの作戦に誰もが絶望を持っていました。
そして案の定敵哨戒機に発見され、3月1日には直掩機の防御を突破して行われた水平爆撃で【旭盛丸】が早くも沈没。
今日は助かった、しかし明日助かるかは誰にもわからない。
僚艦の沈没は、自分の命の終わりが目前であることを知らしめていました。
そして2日の空襲は何とか喪失艦なく切り抜けましたが、3月3日に惨劇というのも生温い、流血地獄が展開されました。
【B-17】と【B-25】による水平爆撃が船団に降り注ぎ、直掩機はこれを護衛してきた【P-38】などの戦闘機にまとわりつかれて爆撃機の撃墜を邪魔されます。
戦闘機同士の戦いが起こるということは爆撃機はそれだけフリーになりますから、船団はなおさら危険です。
しかもこの戦いでは、双発爆撃機にとって一般的な水平爆撃ではなく、新たに実施された反跳爆撃という、水切り石の要領での横からの爆撃も船団を食い荒らしました。
初めて目にする攻撃、そして次の瞬間には絶命。
この経験したことのない爆撃、恐怖に船団は混乱し、次々と被弾していきます。
爆発炎上する輸送船、呻き声がこだまする海面、そして掃射される機銃、ビスマルク海は地獄絵図と化しました。
【時津風】にはその反跳爆撃の爆弾が右舷機関室付近に突っ込みます。
魚雷でも受けたのかというほどの馬鹿みたいにでかい穴をあけた反跳爆撃による爆弾は、機関室の兵士たちをバラバラにし、そして一瞬で浸水させました。
身動きが取れなくなった【時津風】から司令部を移すために【雪風】が接近します。
空襲の合間を縫ってこの移乗は成功しましたが、そこかしこで【時津風】と同様の運命をたどる船がありました。
特に輸送船は最終的に残存7隻全てが沈没。
駆逐艦も【白雪】【朝潮】【荒潮】が縦横の立体的な爆撃に晒されて沈没してしまいました(時系列無視)。
【時津風】は心臓部が吹き飛んで全く動けない状態ではありましたが、こちらは逆に放置していても沈みそうにはありませんでした。
何事もないのであれば曳航もチャレンジしたいでしょうが、場所が場所なので二次災害になりかねません。
【時津風】もまた、キングストン弁が開けられてここで自沈処分される運命となります。
30分にも満たない空襲で壊滅した輸送船団。
青い海、黒い重油、赤い血液。
そんな中で必死に生き続けている人たちの救助は生存した【雪風】らに救助されましたが、潮の流れも早かったことからここでも多くの命が失われてしまいます。
【時津風】の生存者も【雪風】や【初雪】に救助され、ラバウルに引き揚げていきました。
しかし【時津風】はなかなか沈みませんでした。
翌日になって【時津風】が漂流しているのが発見されて、急いで【零式艦上戦闘機】と【九九式艦上爆撃機】がラバウルから飛び立ちました。
【時津風】を発見すると爆撃を加えますが、ところがこれがほとんど命中せず、1発だけ命中しましたがこれでも【時津風】は沈みませんでした。
これじゃあまずいということで今度は潜水艦の派遣が決定。
ところが引き返した後にアメリカ軍機が現れて、見事に【時津風】に爆撃を加えて沈めることに成功します。
日本側の懸念は払拭されました。
ですが潜水艦の派遣は続行されます。
【伊17】や【伊26】【呂101】とラエからの【大発動艇】が同海域にやってきて生存者の救助にあたりました。
連合軍側は日本の生存者も救助せずにバンバン銃殺しており、4日以降に救助された者たちは本当に強運の持ち主だったと言えるでしょう。